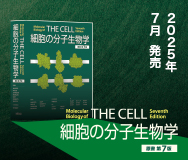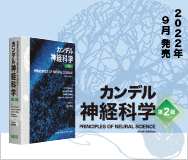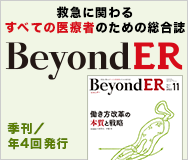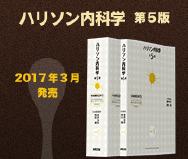Hospitalist(ホスピタリスト)2024年2号
特集:薬物治療の質向上
質の高い患者ケアを支える処方マネジメントのエッセンス
目の前の患者に提供されている薬物治療の質は担保されているのだろうか? 高齢患者やマルチモビディティの患者の増加に直面している医療現場で、このような疑問を抱くこともしばしばあるのではないでしょうか。
医療の質を測定するための指標をみてみると、標準治療やガイドラインなどで勧められていることを患者にしっかり提供しているかどうかが評価項目として多いことがわかります。しかし特に高齢者医療においては、その標準治療が患者本人にとってベストとはいえないこともしばしばあり、やはり個別化という視点も欠かせません。
薬物治療は内科診療を支える柱の1つであり、その質向上というテーマはそこにかかわる医師/薬剤師が共有すべき課題であることは間違いありませんが、そのような知識をまとめた教材はなかなか見当たらないのが現状です。
そこで本特集は、3つのパート、すなわち、Part 1「薬物治療の質を語るうえで知っておきたい知識と実践例」、Part 2「薬物治療を適切に個別化するための基本知識」、Part 3「薬物治療の質向上のために必要なスキルおよび考え方」で構成し、医療の質の話題にふれつつ、薬物治療の質向上や適切な個別化を目指すために必要となる知識・スキルをまとめました。
各トピックは医師と薬剤師が協働するうえでの共通言語になると考えています。本特集を通して国内における医師と薬剤師の協働をもっと意義あるものにしていきたい、そんな願いも込められています。
***********
期間限定公開!
はじめに
「質の高い患者ケアを支える処方マネジメントのエッセンス:質向上とそのための協働,さらに先にあるもの」
→こちらから
***********
はじめに|質の高い患者ケアを支える処方マネジメントのエッセンス:質向上とそのための協働、さらに先にあるもの
榎本 貴一 練馬光が丘病院 薬剤室
Part 1 薬物治療の質を語るうえで知っておきたい知識と実践例
1. 薬剤師とホスピタリストが導く、持続可能な医療の質の改善:薬剤関連の診療評価指標(QIs)を理解しよう
小坂 鎮太郎 東京都立広尾病院 病院総合診療科
2. 薬物治療の質担保のために医師と薬剤師はどのように協働できるか:
Case 1:診断プロセスにおける協働
綿貫 聡 東京都立多摩総合医療センター 救急・総合診療科
榎本 貴一
Case 2:回復期リハビリテーションにおける協働
松本 彩加 熊本リハビリテーション病院 薬剤部
吉村 芳弘 熊本リハビリテーション病院 リハビリテーション科
Case 3:診療科配属の薬剤師との協働
永倉 史子・小坂 鎮太郎 東京都立広尾病院 病院総合診療科
3. 米国における臨床薬剤師の業務:医療の複雑化のなかで医師と薬剤師のタスクシェアを考えるために
小崎 彩 School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences、 University of California、 Irvine
[コラム①]医療安全の専従薬剤師や薬剤部門の管理職と薬物療法の質向上:病院機能における重要な視点に関与する
川名 賢一郎 聖路加国際病院QIセンター/薬剤部
Part 2 薬物治療を適切に個別化するための基本知識
4. 薬物動態:吸収、分布、代謝、排泄:臨床での意思決定に影響し得るものを中心に
門村 将太 JCHO北海道病院 薬剤部
5. 薬物相互作用:薬物動態学的に、特に臨床で注意しなければならないものを中心に
土岐 真路 聖マリアンナ医科大学病院 治験管理室
6. 薬剤アレルギー:病態、アレルギー歴の聞き取り、被疑薬の管理
小澤 廣記 聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center
7. 薬物血中濃度モニタリング:医療チームで議論するための共通言語として
花井 雄貴 東邦大学薬学部 臨床薬学研究室
8. 腎不全患者の薬剤投与:個別化を適正に行うために
柴田 啓智 済生会熊本病院 薬剤部
[コラム②]肝疾患や肥満患者での薬剤投与:投与量は通常量と同じでよいのか?
浜田 幸宏 高知大学医学部附属病院 薬剤部
9. 妊婦と授乳婦に対する薬物治療:臨床的に問題となるケースは限られている
加陽 直貴 しろわクリニック
岩田 智子 浜松医科大学 産婦人科家庭医療学講座
城向 賢 菊川市立総合病院 産婦人科/静岡家庭医養成プログラム
[コラム③]今さら聞きづらい処方から投与までのお作法
①処方時の7つのQ&A
森 裕也 東京ベイ・浦安市川医療センター 薬剤室
②投与時の10のQ&A
鈴木 慶介 台東区立台東病院 薬剤室
[コラム④]錠剤の嚥下の可否はどのように決まるか?:メカニズムを学びながら、摂食・嚥下のコツを見つけよう
林田 裕貴 ごはんがたべたい。歯科クリニック
松本 朋弘 上野原市立病院 内科
Part 3 薬物治療の質向上のために必要なスキルおよび考え方
10. 薬物治療とEBM:まずは「活用モード」のEBM実践を習得しよう
本田 優希 浜松医科大学 地域家庭医療学講座/聖隷浜松病院 総合診療内科
11. 臨床推論:薬物有害事象かどうかを適切に判断する
原田 侑典 獨協医科大学病院 総合診療科
[コラム⑤]処方のアウトカムは何か考える:予後とtime to benefitの関係、患者の価値観を考慮した設定が大事
原田 洸 Brookdale Department of Geriatrics and Palliative Medicine、 Icahn School of Medicine at Mount Sinai
12. ポリファーマシー:減薬の方法と注意点
中込 哲 山梨大学医学部附属病院 薬剤部
[コラム⑥]漢方はどんな場面で使用すべきか?:「効果が期待できる場面のリスト」として臨床研究を役立てる
吉野 鉄大 慶應義塾大学医学部 漢方医学センター
13. ケア移行時のmedication reconciliation:常にハイリスクな状況であることを認識しつつ、正確な情報の移行を行う
安本 有佑 板橋中央総合病院 救急総合診療科
14. 患者への薬剤に関する説明と患者エンゲージメント:患者が病気とどう共存していくかに大きくかかわる
平田 一耕 亀田総合病院 薬剤部
【連載】
ホスピタリストとエキスパートで深読み! 診療を変える最新論文:第1回 STEP-HFpEF試験
安本 有佑
辻本 泰貴・廣田 勇士(神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学)
佐藤 宏行(東北大学病院 循環器内科)
Clinician Update
官澤 洋平・石丸 直人 愛仁会明石医療センター 総合内科
-
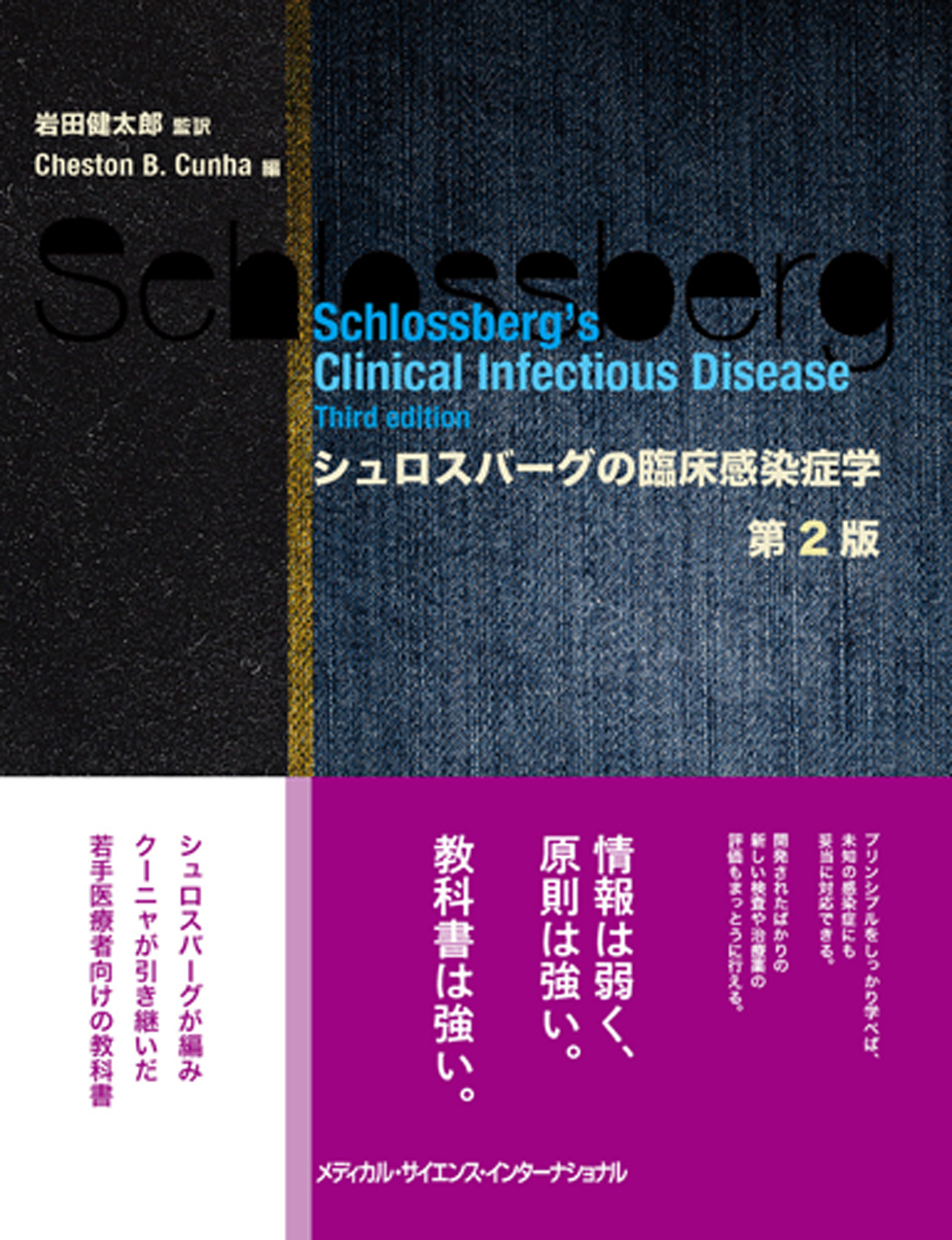
- シュロスバーグの臨床感染症学 第2版
- ¥25,850
-
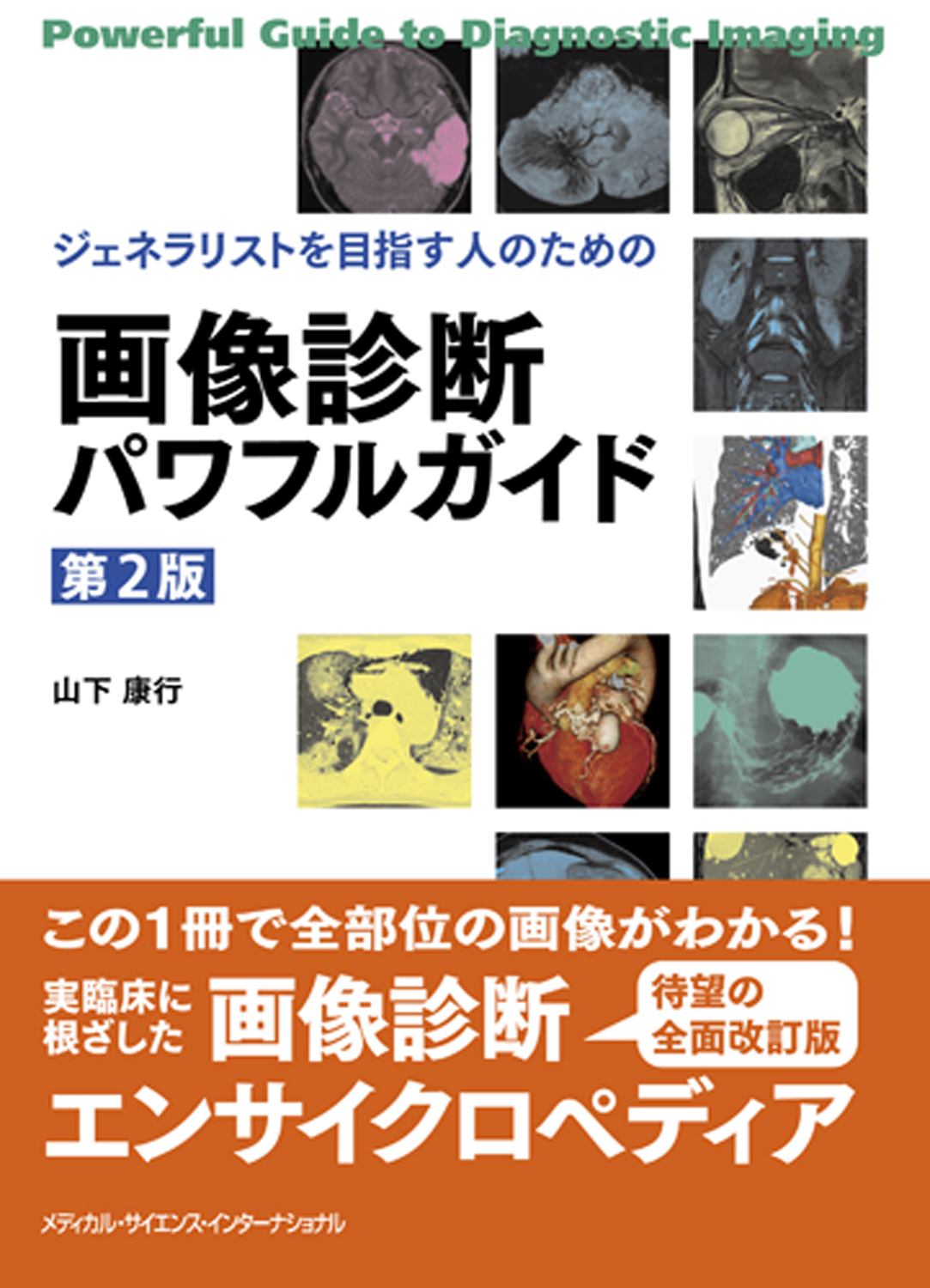
- ジェネラリストを目指す人のための 画像診断パワフルガイド 第2版
- ¥12,100
-
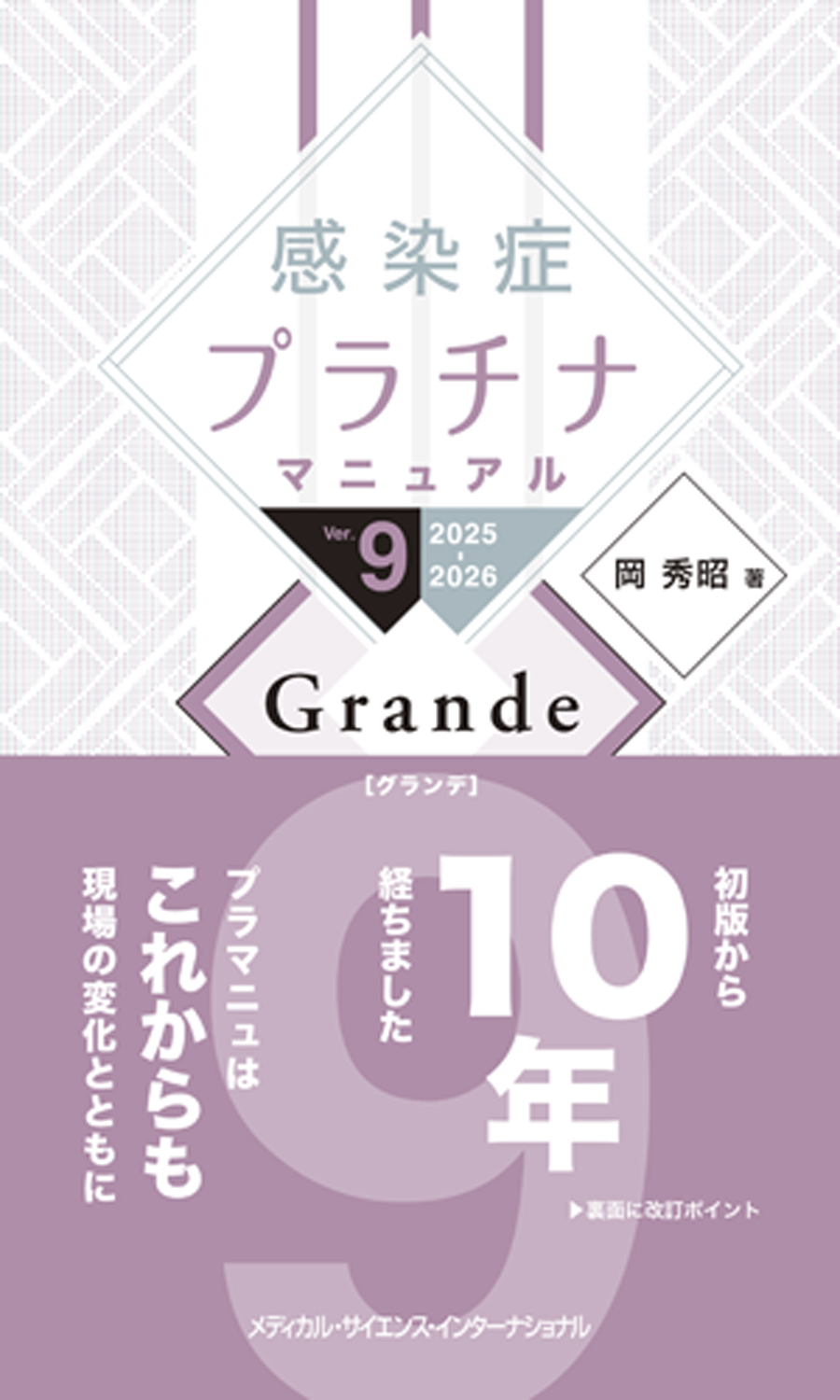
- 感染症プラチナマニュアル Ver.9 2025-2026 Grande
- ¥4,180
-

- 麻酔科臨床SUMノート 第2版
- ¥8,250
-
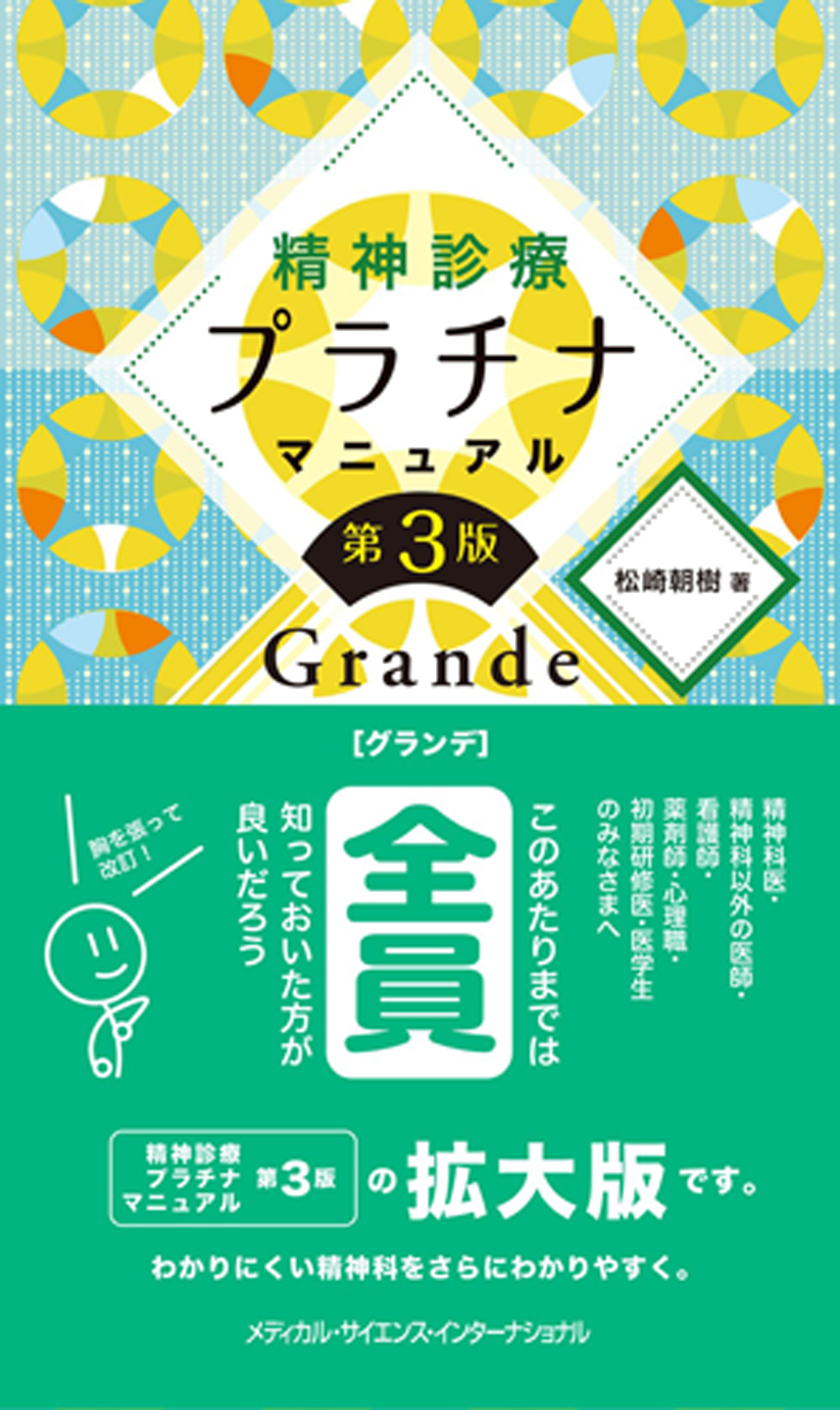
- 精神診療プラチナマニュアル Grande 第3版
- ¥3,960
-
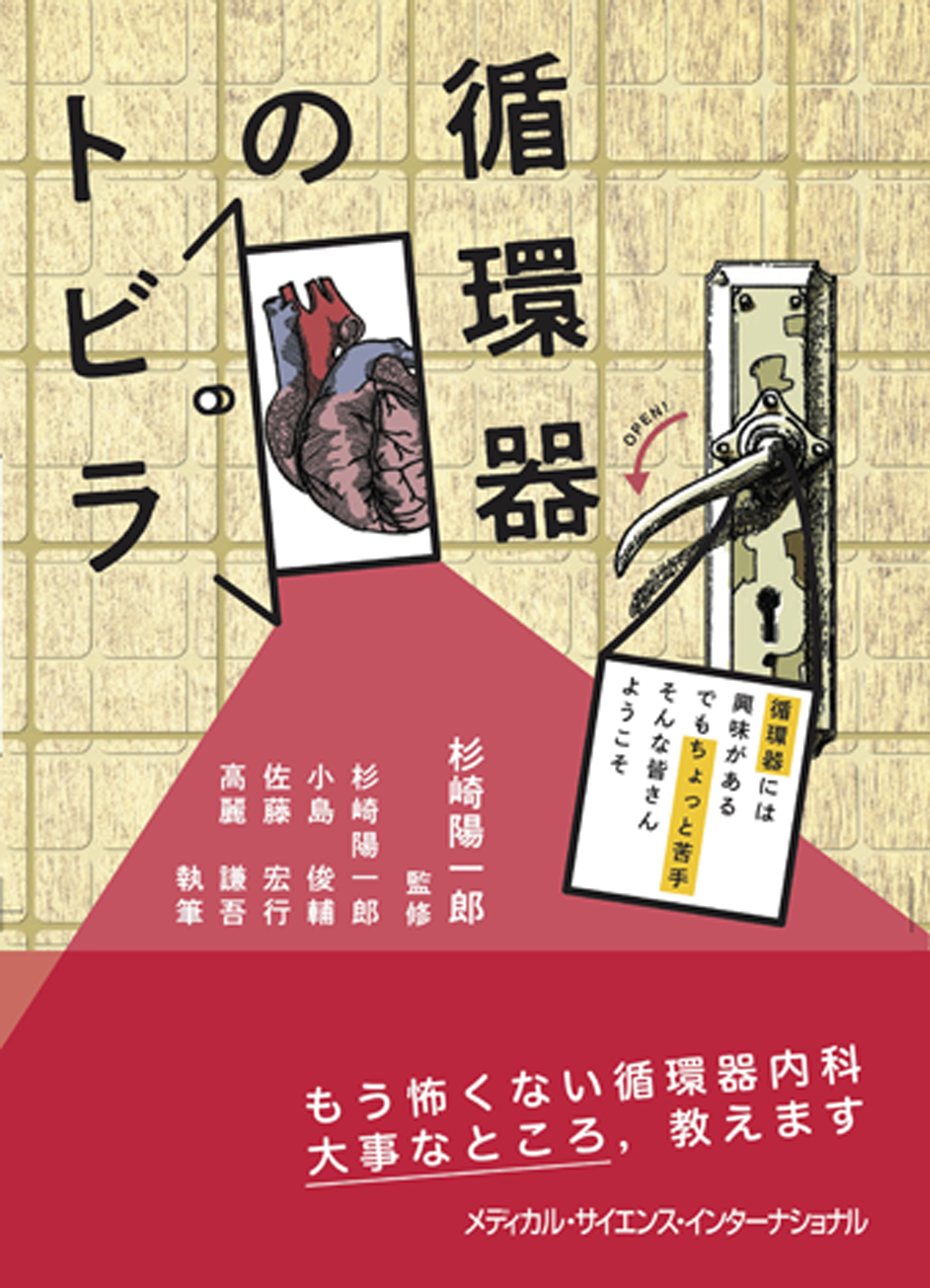
- 循環器のトビラ
- ¥5,940
-
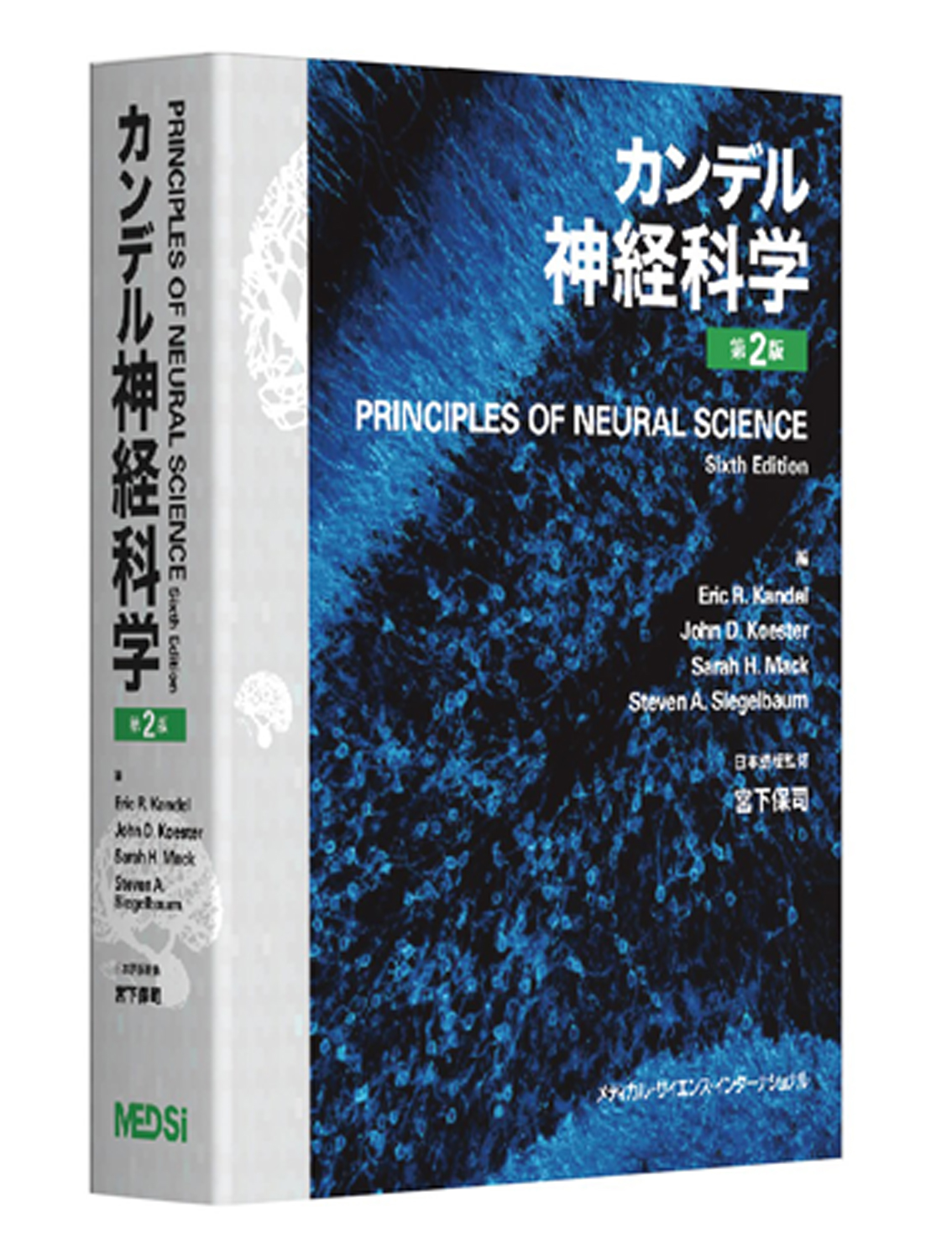
- カンデル神経科学 第2版
- ¥15,950
-
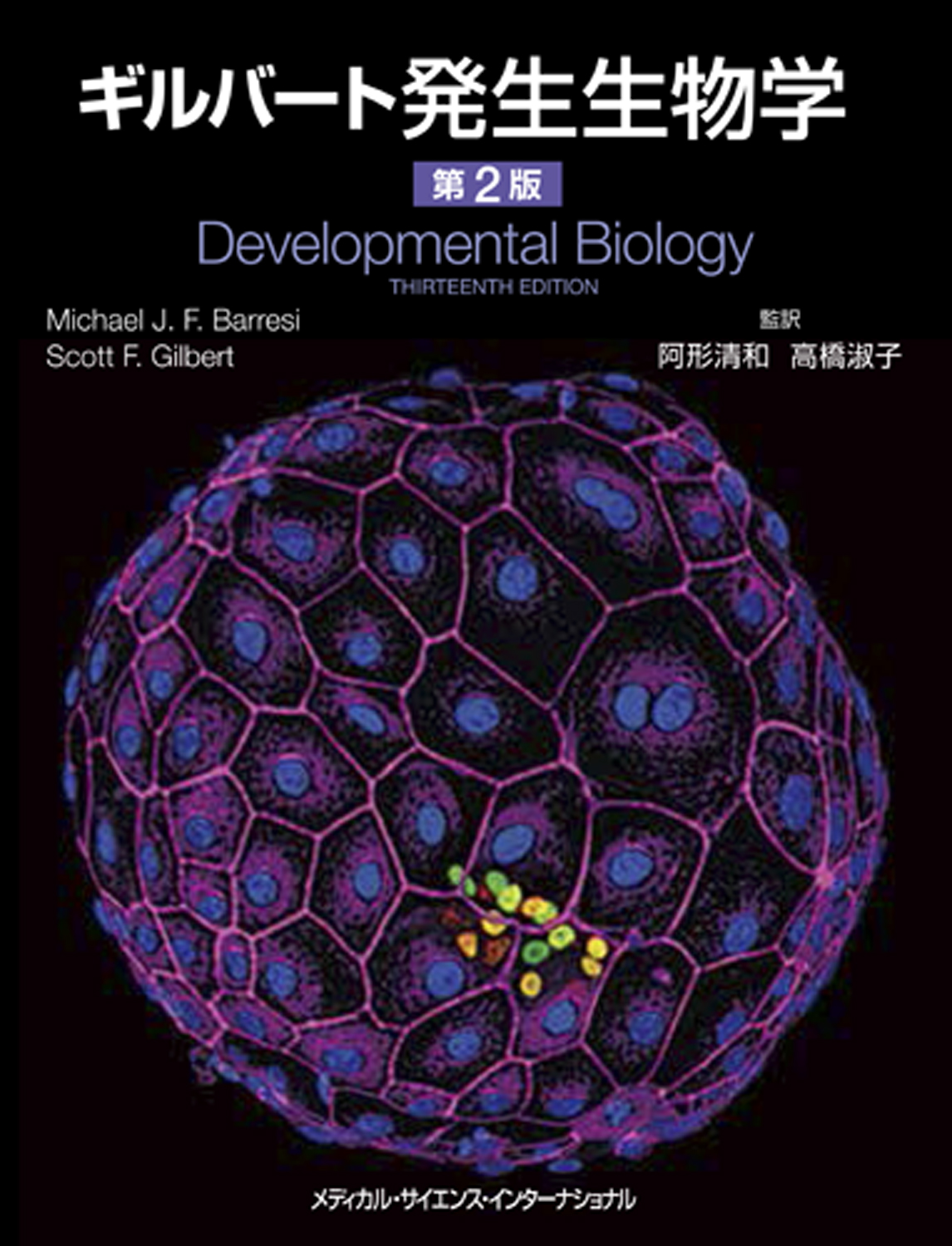
- ギルバート発生生物学 第2版
- ¥13,750
-
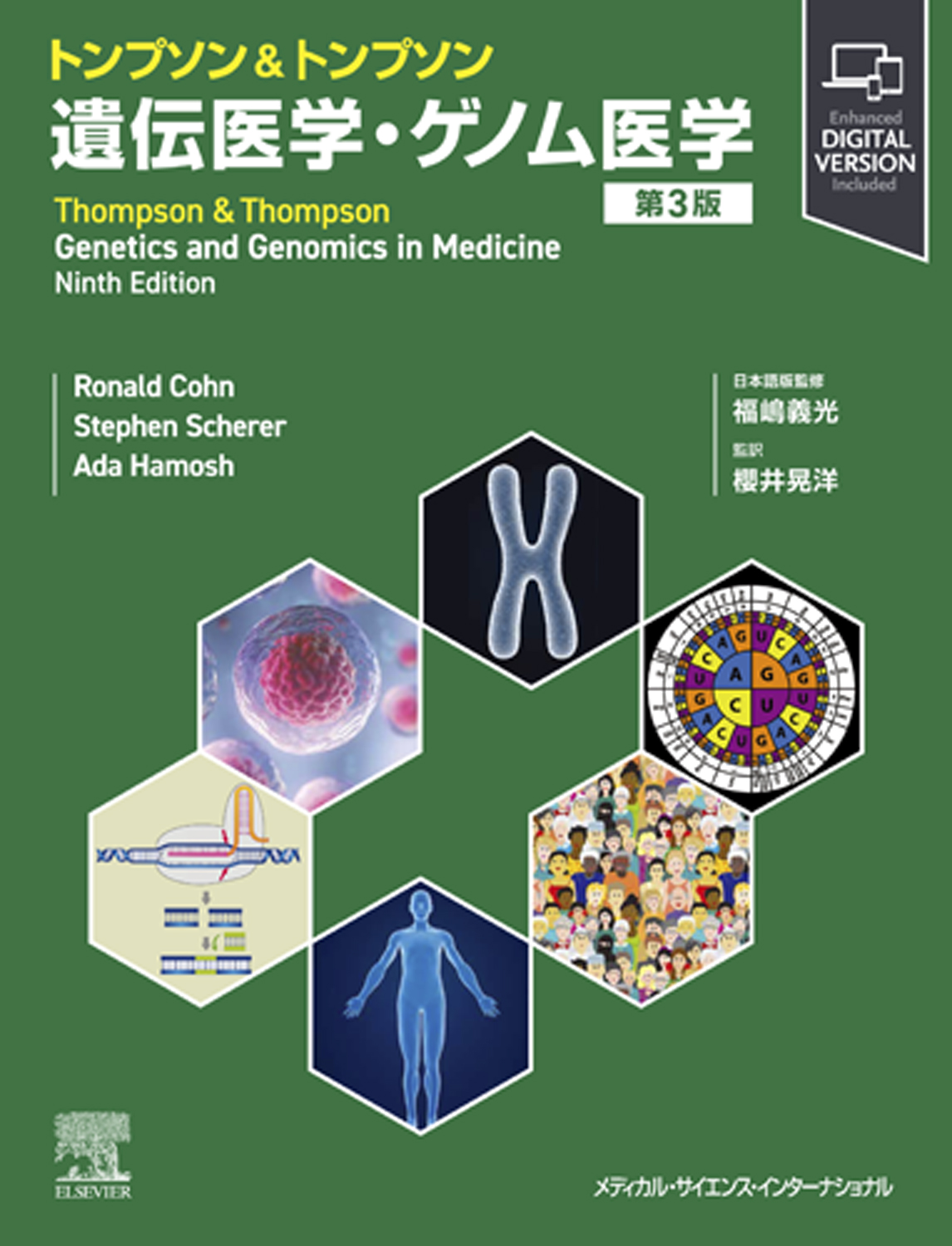
- トンプソン&トンプソン遺伝医学・ゲノム医学 第3版
- ¥12,100
-
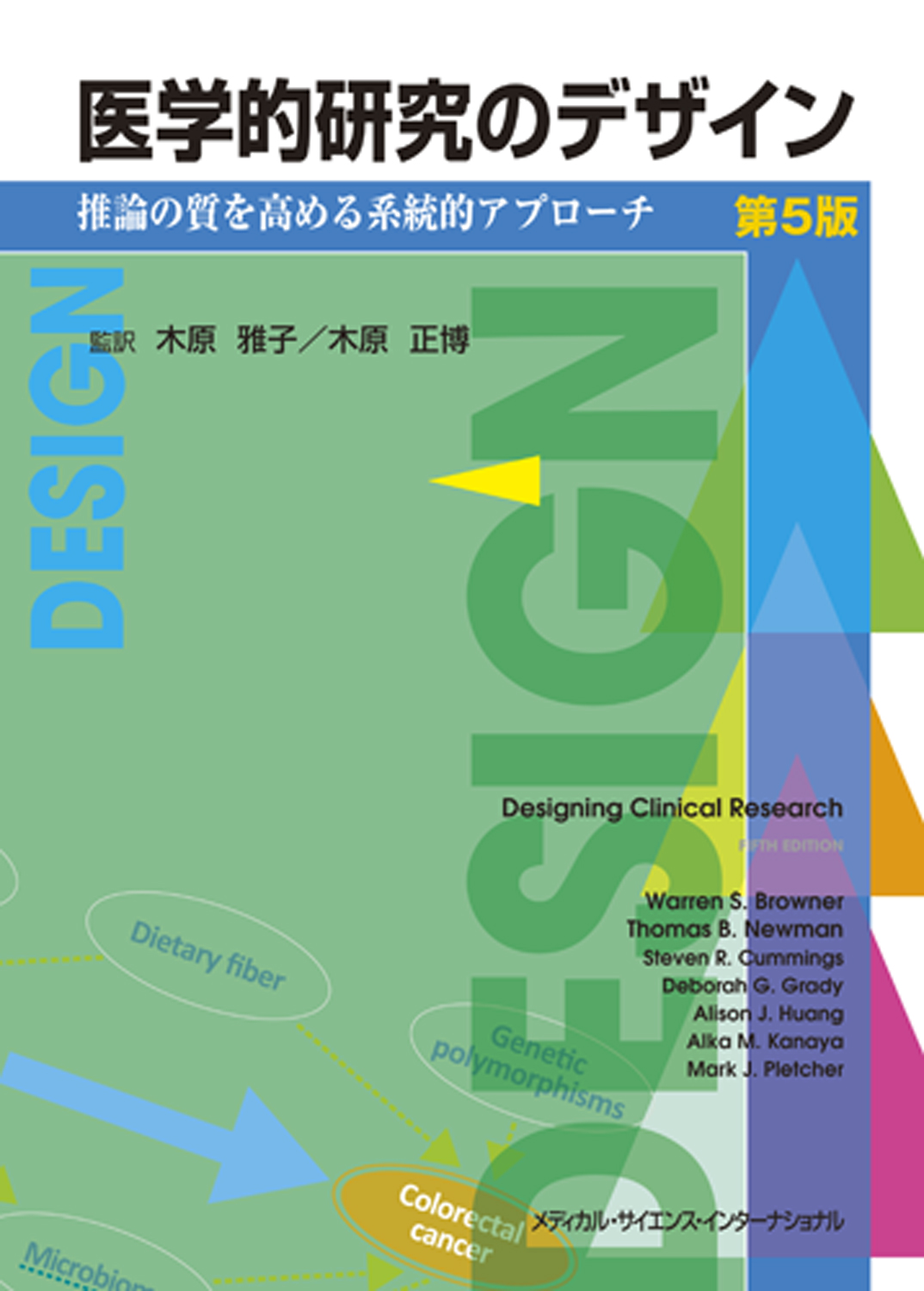
- 医学的研究のデザイン 第5版
- ¥6,270
-
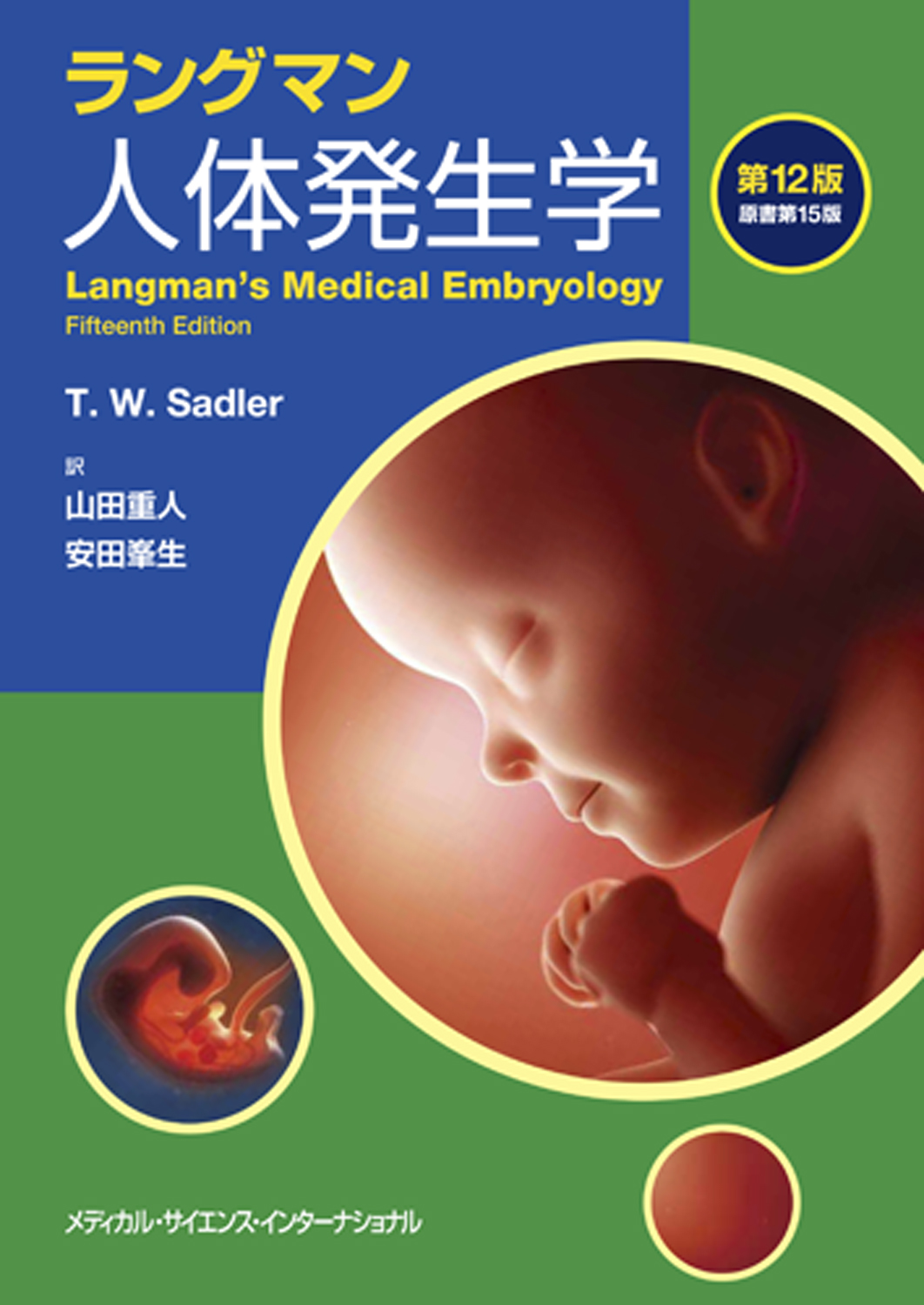
- ラングマン人体発生学 第12版
- ¥9,350
-

- カラーで学ぶ解剖生理学 第2版
- ¥6,160
-
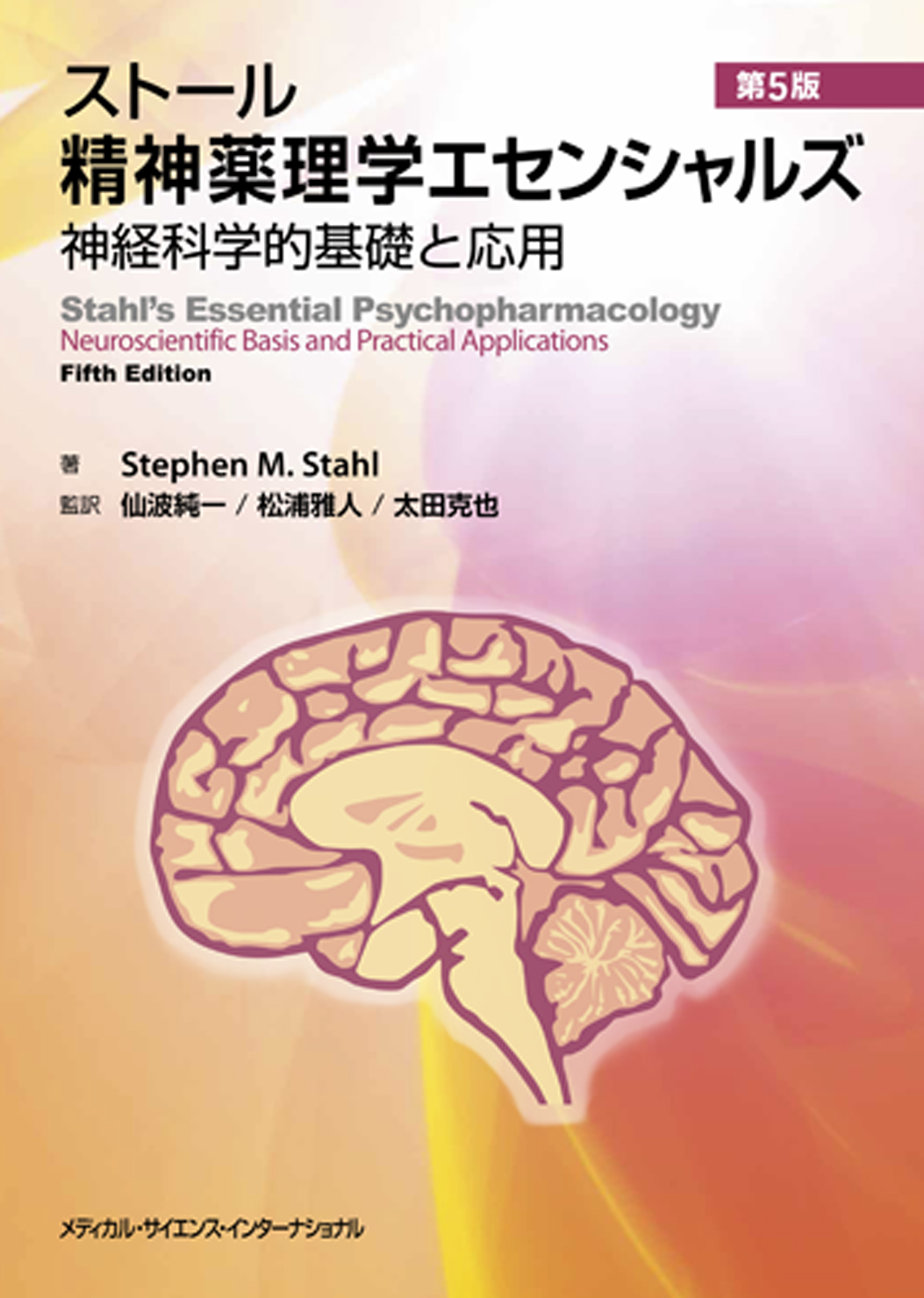
- ストール精神薬理学エセンシャルズ 第5版
- ¥13,750
-
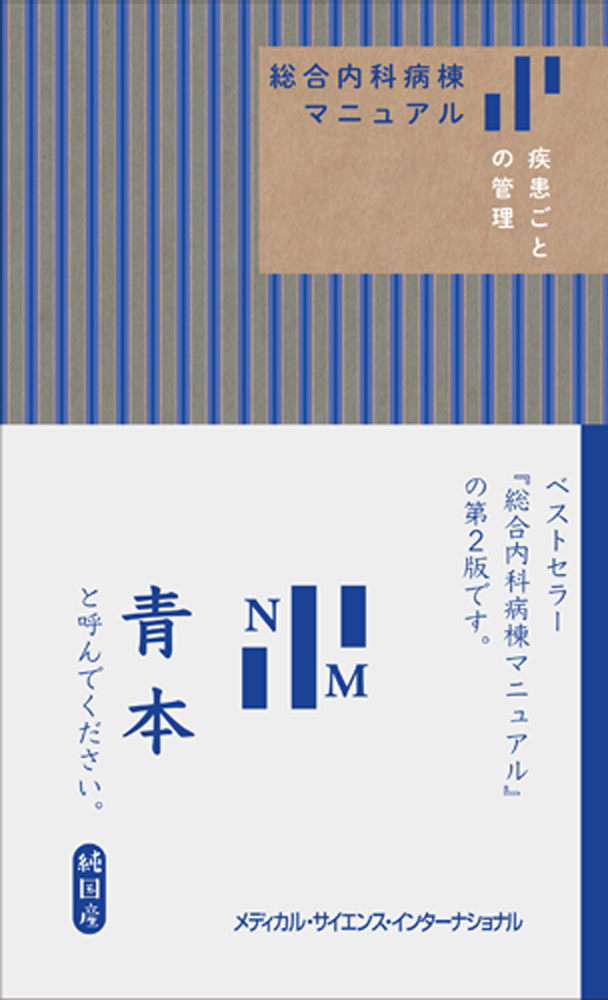
- 総合内科病棟マニュアル 疾患ごとの管理(青本)
- ¥6,160
-
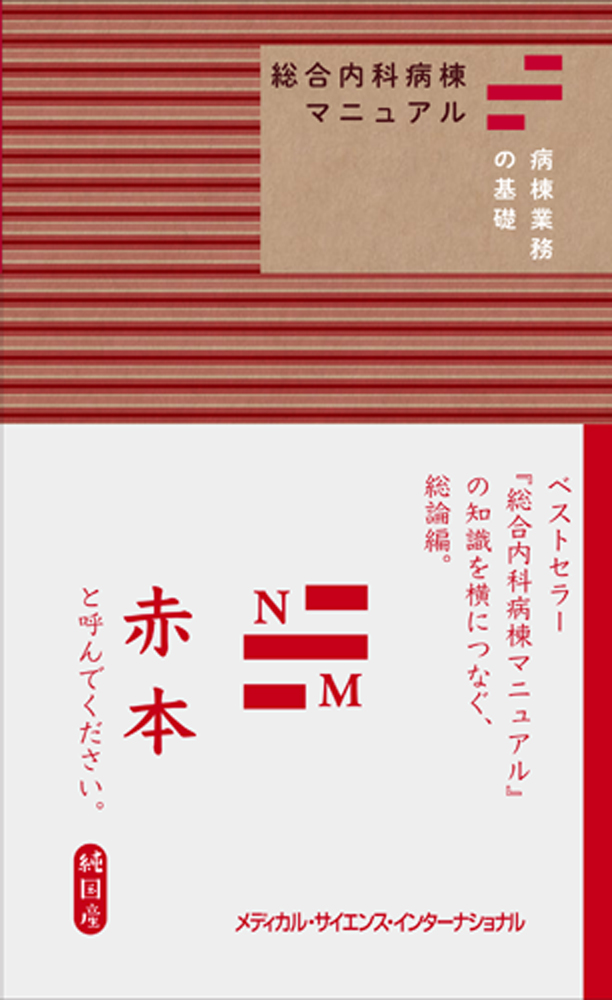
- 総合内科病棟マニュアル 病棟業務の基礎(赤本)
- ¥4,840
-

- 重症患者管理マニュアル
- ¥7,150
-

- エッセンシャル免疫学 第4版
- ¥7,150
-
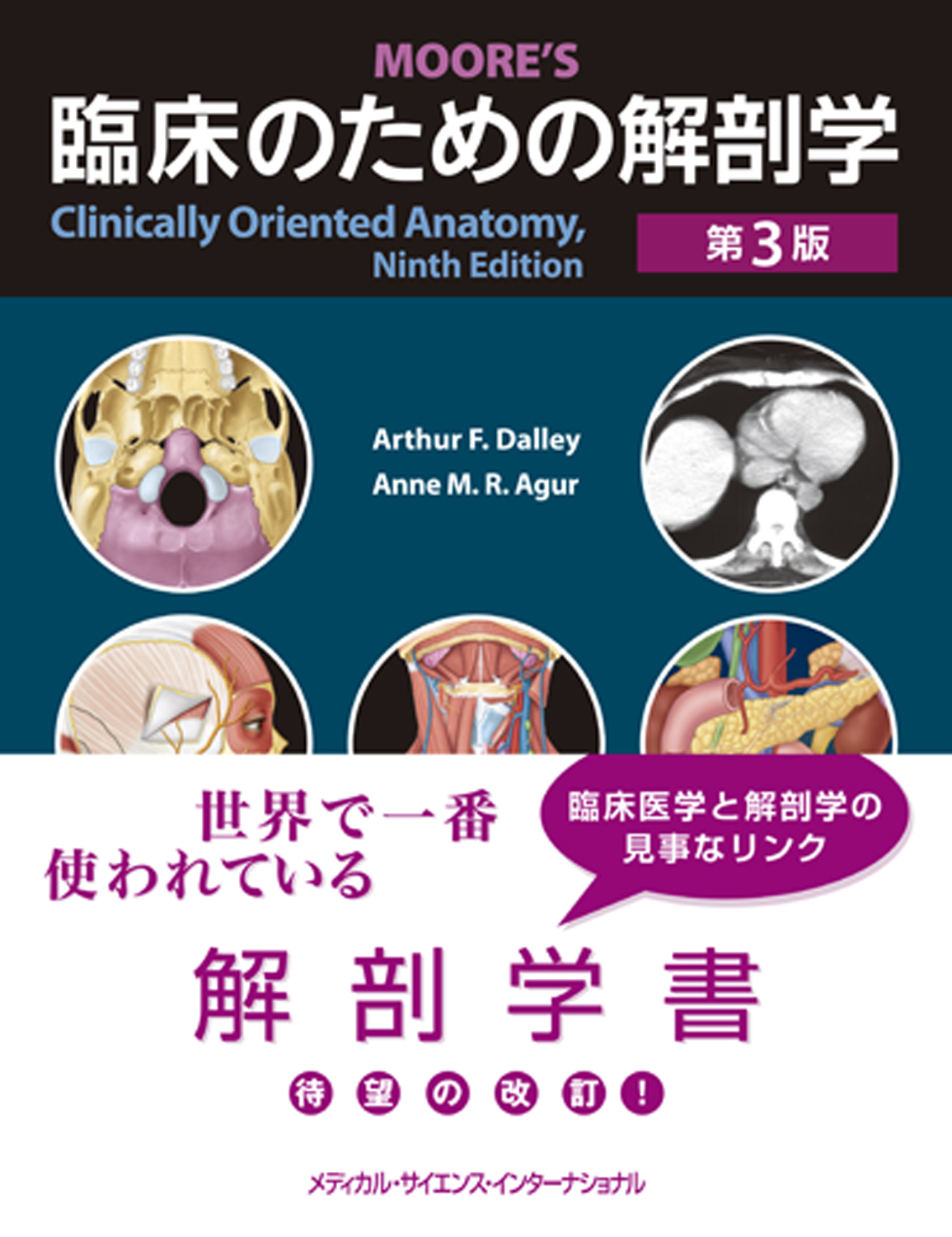
- 臨床のための解剖学 第3版
- ¥15,950
-
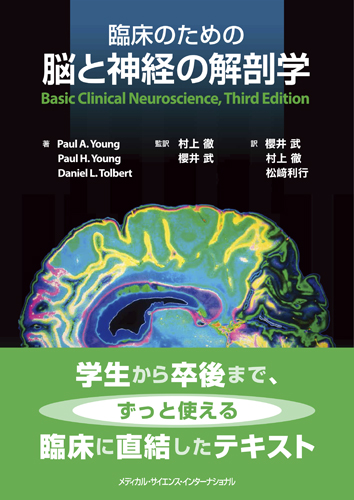
- 臨床のための脳と神経の解剖学
- ¥7,480
-

- MRIの基本パワーテキスト 第4版
- ¥7,150
-
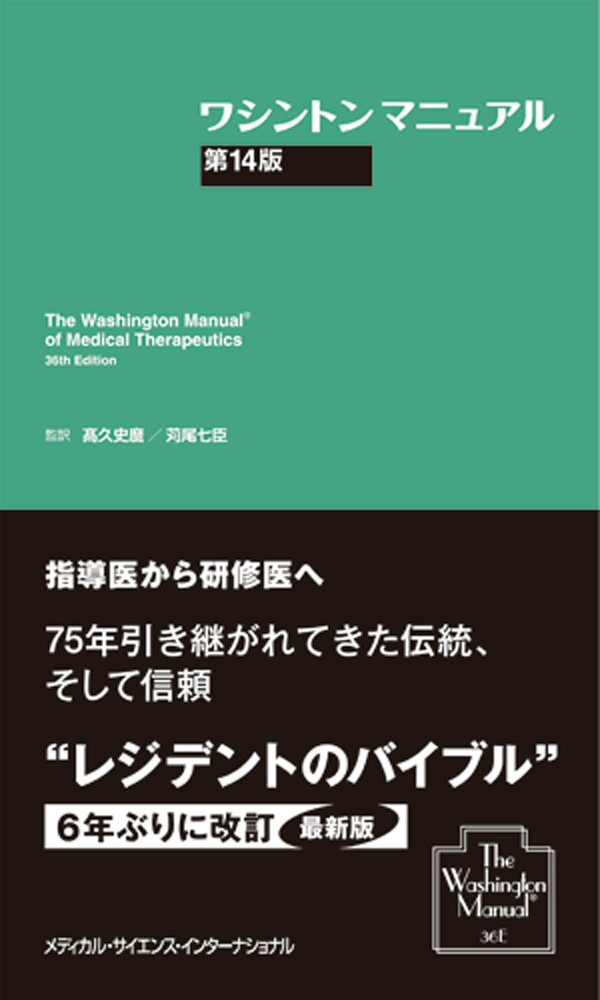
- ワシントンマニュアル 第14版
- ¥9,570
-
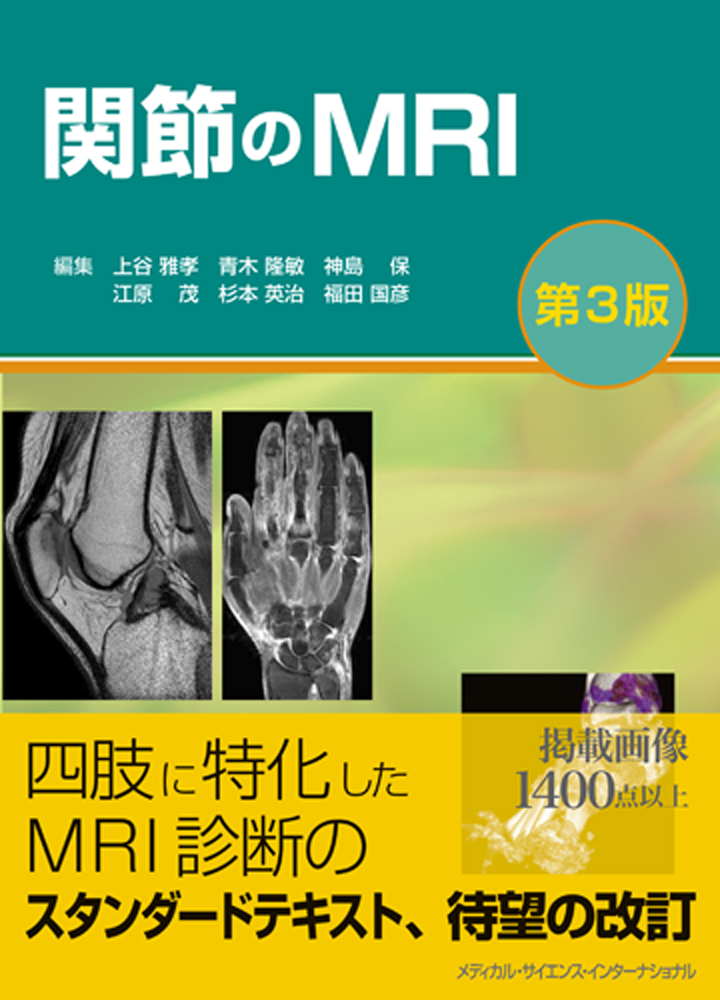
- 関節のMRI 第3版
- ¥14,300
-
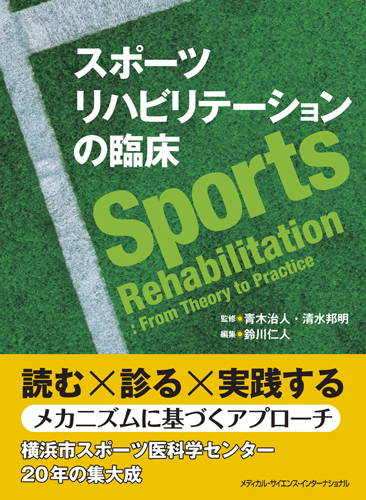
- スポーツリハビリテーションの臨床
- ¥7,700
-
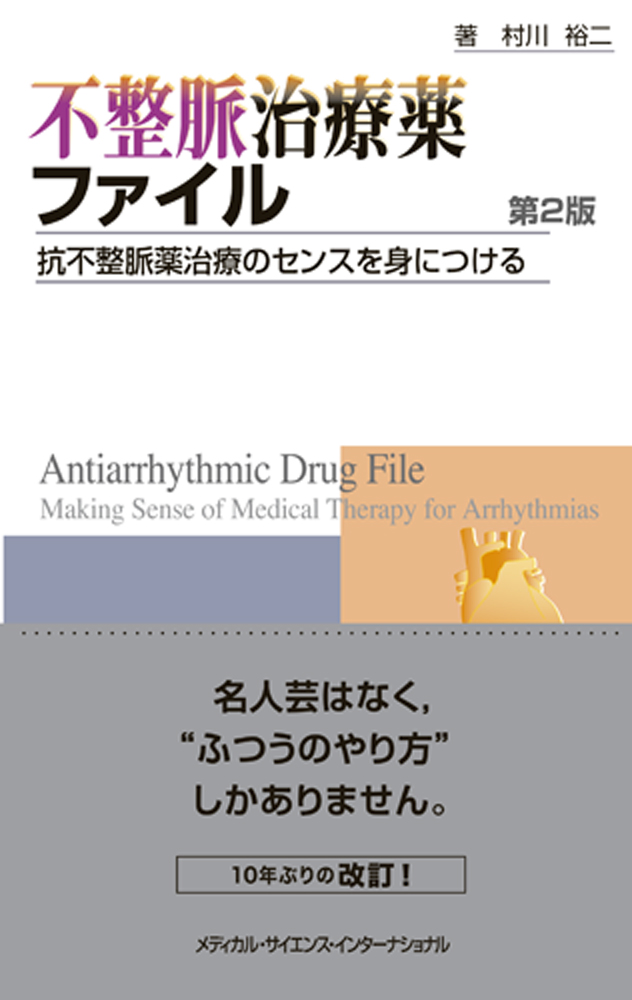
- 不整脈治療薬ファイル 第2版
- ¥5,500
-
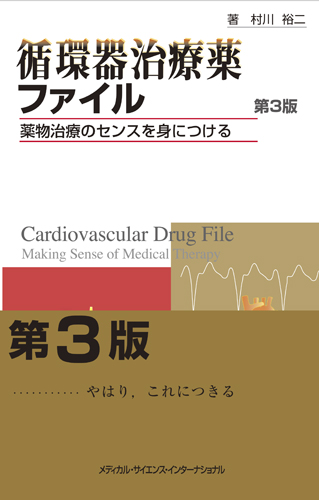
- 循環器治療薬ファイル 第3版
- ¥7,700
-
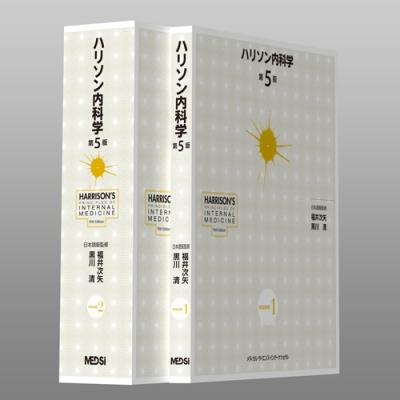
- ハリソン内科学 第5版
- ¥32,780
-
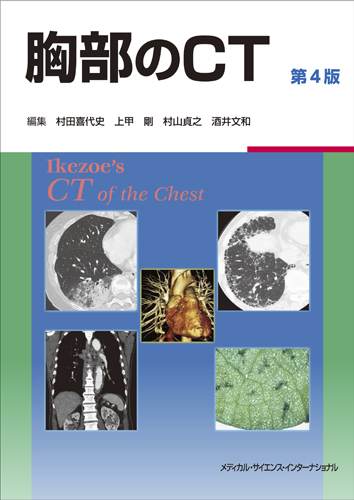
- 胸部のCT 第4版
- ¥16,500
-
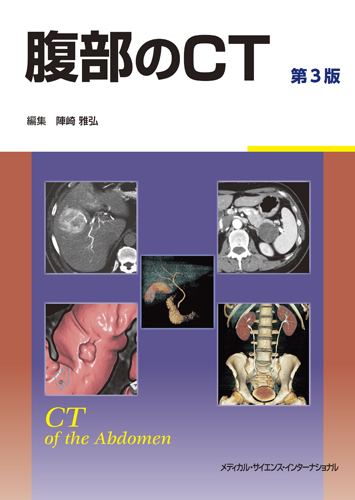
- 腹部のCT 第3版
- ¥14,300
-
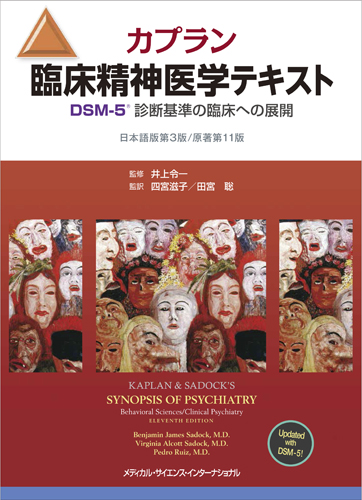
- カプラン臨床精神医学テキスト 第3版
- ¥22,000