誤診の解体 - 診断エラーに潜む認知バイアス -
忘れない、いや、忘れるべきでない
患者さんへ、説明責任を果たすために
その診断エラーは、いかなる認知バイアスや感情バイアスによって引き起こされたか、実際の症例で紐解く。医師の背景や心情、ほかの患者の状況などが具体的に臨場感あふれる筆致で描写されており、読者に追体験をさせながら、意思決定における失敗はなぜ起きたのか、どのような認知エラー誘発状況があったのかひとつひとつ丁寧に解き明かす。まさに「認知的剖検(Cognitive Autopsy)」である。あらゆる診療科の医師、研修医を正しい診断と診療プロセスに導くガイドブック。
はじめに
症例1 サイレント ホワイト クリスマス
症例2 落ち着きましょうか
症例3 クォーターバック サック
症例4 誰のための安心か
症例5 出る息,入る息を 待たず
症例6 ベッドコントロールプレッシャー
症例7 平然たる英国風紳士
症例8 黄泉がえり
症例9 飛べ! 模型飛行機
症例10 皮疹に注目!
症例11 パーフェクト・ストーム
症例12 帰っていった ヨッパライ
症例13 産後の肥立ち
症例14 盲目の眼科医
症例15 偽りの偽発作
症例16 常連さんたち
症例17 聖母の苦しみ
症例18 肘を折られて良医となる
症例19 ミシュランレディ
症例20 お抱え運転手
症例21 逆St. Elsewhere症候群
症例22 退役海軍兵の憂鬱
症例23 飲み込みにくい話
症例24 熊手物語
症例25 親しき仲にも手順あり
症例26 若かりし日の思い出
症例27 ストーマトラブルメーカー
症例28 二輪物語
症例29 一人で何役?
症例30 疾風迅雷
症例31 屋上屋を架す
症例32 消えたガイド
症例33 夜明け前が一番暗い
症例34 パートナーのお手柄
症例35 ファスト & スロートラック1
症例36 似て非なるもの
症例37 危ないニアミス
症例38 石につまずく
症例39 そう甘くない!
症例40 筋違いの診断
症例41 見逃し
結論 臨床判断を改善するための戦略
付録 メタ考察
付録 バイアスとその他の認知的要因に関する用語集
索引
注
忘れられない患者が誰にもいる
もうずいぶん前のことになる。卒後数年目の若手医師Aは,ある地方のクリニックに勤務していた。このクリニックはこの地域の唯一の医療機関であり,2次救急患者を受け入れる病院は険しい山道を登って車で30分のところ,3次救急患者を受け入れる病院は海岸の曲がりくねった細い道を小一時間かけていったところにしかなかった。Aは地域で熱心に医療に取り組み,住民から信頼を得つつあった。住民の一人である70代女性Yさんは,独身のAが食事の用意に苦労しているだろうと気遣って,毎日のように夕食のおかずを,診療が終わった1時間後に届けてくれていた。笑顔でおかずを届けてくれるYさんとたわいもない話をすることは,Aの毎日の楽しみであった。
ある嵐の日の深夜2時。Yさんが急に背中をひどく痛がっているので診てほしいと,Yさんの夫から電話が入った。Aはクリニックを開けてYさんを待った。しばらくすると,どしゃぶりの雨の中,雨よけのシートをかぶせられ,リアカーに乗せられたYさんがずぶ濡れの夫によって運ばれてきた。真夜中のことだったので,近所の人に車を出してもらうことをためらったようであった。Aは二人のことを気の毒に思った。
Yさんはクリニックに通院してはおらず持病はないはずであった。尿管結石,胆嚢炎,急性冠症候群,解離性大動脈瘤がAの頭の中をよぎった。Yさんは右の肩甲骨の下付近の痛みを訴えており,圧痛はなかった。心雑音はなく,呼吸音の副雑音もなかった。クリニックにはリニアプローブしかついていない年代物の超音波装置しかなかったが,これで水腎症,胆嚢腫大,肝内胆管拡張がないこ,少なくとも心収縮の局所的な低下や大動脈基部の拡張と同部にはためく構造物がないことを確認した。と同時に,心電図でST-Tの変化を経時的に観察した。胸部X線写真では大動脈の拡張はないように思えた。クリニックに血液検査機器はなく,これ以上の検査はできなかったが,ひとまず明らかな重篤な疾患はなさそうだとAは思った。2次病院か3次病院に搬送して精査してもらうべきだろうか? Aは迷った。というのも,先日,崖から転落した小学生を土曜日の正午ごろ3次病院に精査の依頼をした際に,意識状態が良いなら経過を診て良い,とけんもほろろに断られ,非常に嫌な気持ちになっていたからだ。Aは朝7時まで鎮痛処置をしながらYさんの経過を診たところ,痛みはほとんどなくなっていったので,クリニックの往診車でYさんを自宅まで送り届けることにした。
その日のクリニックには,朝8時から大勢の外来患者が待ち受けていた。外来をしながらもAはYさんのことが頭から離れなかった。やっと手が空いた午後2時,Aは往診車を飛ばしてYさんのもとに赴いた。Yさんは床に臥せて休んでいたが,いつものような笑顔で迎えてくれたのでAはほっとした。また夜に様子をみに来ると言ってAはクリニックに戻った。午後の外来が終わろうとしていた17時半ごろ,Yさんの夫から取り乱した様子でクリニックに電話が入った。薬を飲もうとして床から起き上がった瞬間にYさんが意識を失ったという。Aは慌ててYさんのもとに駆け付けた。すでに心肺停止状態であった。必死に心肺蘇生を試みたが,そのかいはなかった。ああ,なんということだろう。昨晩の痛みは何らかの急性の血管病変によるものだったに違いない。解離性大動脈瘤だったのだろうか。Aはその場で脱力してしばらく動けなかった。
その日の夜,Yさんの通夜が営まれていたが,AはYさんのもとに行くことができなかった。何という不義理なことだろう。Aは宿舎でひとり,2日前にYさんが届けてくれたおかずを大事に少しずつ口にしたが,いつものおいしい味を感じることはできなかった。翌日,葬儀が営まれた。Aは集まった人たちの最後尾にひっそりと立って静かに手を合わせた。心の中でYさんに何度も何度も頭を下げて謝った。
“ああ,私が誤診したのだ。私がYさんを救えなかったのだ” 涙がこぼれそうになるのをぐっと我慢して,葬儀の間中,立ち続けた。皮肉にも,あの日の夜とはまったく異なる穏やかな青い海と晴天の青空がYさんの自宅の向こうに広がっていた。若手医師Aに限らず,おそらくすべての医師には忘れようとしても忘れられない,いや,忘れるべきでない診断エラーの症例と患者さんの顔や言葉が心に残っているはずである。自分の診断エラーケースを皆で共有して建設的に検討することはなかなか難しい。恵まれた学習環境であれば同僚とともに建設的にエラー症例を検討し,そこから学び,次の臨床につなげていこうとする努力がされていることもある。しかし,患者さんに致命的な害があったケースを担当した医師がその症例について事細かに提示することは勇気のいることであり,実際,あまり行われることがないように思われる。しかしながら,次の臨床のためにきちんと症例を振り返って,エラー防止につなげるべきである。それがわれわれ医師の,患者さん,さらには社会に対する説明責任とも言えるだろう。
2007年にある雑誌で臨床推論の特集があり,「正しい臨床判断のための認知心理学」という副題で寄稿することがあった。この時私は初めて診断エラーについての研究が海外では行われていることを知り(Arch Intern Med 2005; 165: 1493-9),診断エラーの分類と頻度,代表的なヒューリスティックとバイアスについて紹介した。その後,細々と診断エラーに対する関心を高めようと活動していたが,力不足でなかなかその機運が高まることはなかった。2011年に臨床推論過程を症例ベースで解説する書籍を出版する機会があり,その際に本書の原著者Pat Croskerry博士の論文に遭遇した(Acad Emerg Med 2002; 9: 1184-204)。そこには認知反応傾向cognitive
disposition to respond)として約30の認知バイアスが詳細に解説されていた。それを読むと,臨床の世界の霧が晴れて見通しがよくなるように感じ,自著でそれを引用紹介した。その後,少しずつではあるが診断のための認知心理学の知見が知られるようになったように思う。そしてそれから10年たった現在,やっと日本でも診断エラーの教育・研究が活発化しつつある。中堅から若手の総合診療医を中心としたいくつかの活動グループによる取り組みは大変素晴らしいものであり,今後の発展を非常に楽しみにしながら,多くの臨床医が期待をもって見守っている。
さて,本書は私が最も影響を受けた診断エラーの研究者であるPat Croskerry博士による最新刊である。いくつかの総論的な解説とともに,41の実際の症例の詳細な経過提示とその中で生じた診断エラーの分析が行われており,読者はまさにその症例にかかわっているかのごとくの感覚で読み進められるであろう。そして,このような症例提示とその分析について,今後自施設で同様の検討会を行うときの参考になるであろう。ぜひ本書を参考に,診断エラーの認知的剖検(cognitive autopsy)が全国の検討会で広まっていくことを期待したい。
数々の忘れられない患者さんの顔を思い浮かべながら
長久手市の研究室にて
2011年11月
愛知医科大学 医学部 地域総合診療医学寄附講座
宮田 靖志
福島県立医科大学 総合内科・臨床研究イノベーションセンター
中川 紘明
医学の始まり,すなわち先史時代の呪術者の時代から,疾患に関する知識は,最初は口頭で,その後は文字に書き残すことで,物語(narative)として蓄積されてきた。医療従事者にとっての道標は,この物語と試行錯誤から得られた厳しい教訓だけだった。効果があると思われるものがあれば,それを必要な道具として取り入れていた。さまざまな疾患が認知されるようになると,特定の治療法についてコンセンサスがうまれる。過去2世紀の間に,このプロセスは医学文献の出現とともに進化し,医学的管理に重点を置いた症例報告を掲載するという当初の考えを維持している雑誌もある。数十年にわたり,Australian Medical Journal誌に掲載された総合診療医のJohn Murtaghによる連載「Cautionary Tales」は非常に人気があった1)。また,医療過誤の教育的価値に焦点を絞るものもある。Charles Pilcherが編集したオンライン連載「Medical Malpractice Insights」は,不幸な出来事の第一の被害者である患者と第二の被害者である同僚から身をもって学ぶことができる貴重な機会となっている2)。
それらの症例は貴重なものであるが,その焦点が具体的で明白な事実に必然的に限られてしまうことがよくある。有害事象が発生した際の根本原因解析においても同様の制約がある。有害事象の根本原因解析とは,事象の根本原因を明らかにして,適切な解決策を見出すことを目的としている。一般的には,「なぜ」という質問を繰り返しながら,表面的な事象から核心の事象に迫る。例えば,タイタニック号の沈没事故では,「なぜ沈んだのか?」という最初の質問に対して,「側面に穴が開いていたから」と回答できる(表面の原因)。「なぜ側面に穴が開いたのか?」「それは,氷山にぶつかったからである」「なぜ氷山にぶつかったのか?」というように,核心の原因に近づけば近づくほど,解決すべき最終的な原因が見えてくる可能性が高くなるのである。しかし,医療における有害事象の根本原因解析を行うチームのさまざまな問題点3)は,個人の意思決定とその背景にある認知的な問題を十分に扱うことがほとんどないということにある。病歴聴取が不十分だった,あるいは身体診察が不完全だった,という結論に至るかもしれない。これらは有害事象の正当な表面の原因かもしれないが,それぞれの原因を突き止めるためには,より核心の原因まで調べる必要がある4)。なぜ,より詳細な病歴聴取を行わなかったのか? なぜ身体診察が不十分だったのか? などである。
当たり前のことを当たり前以上にできない理由はいくつかあるが,特にWYSIATIというバイアスが思い浮かぶ。WYSIATIとは,Daniel Kahnemanが提唱したWhat you see is all there is(目に見えるものがすべてである)の頭字語である5)。
WYSIATIは,認知的倹約の傾向を表しており,アンカリング,確認バイアス,すべてを分析する原則違反,満足探索など,いくつかの認知バイアスと関連している。このような,大雑把でぞんざいな行動をとってしまう理由としては,時間的プレッシャー,認知的過負荷,ストレス,疲労などがあげられる。これらの理由から,思考のショートカット,ヒューリスティックス,簡略化された方法で意思決定を行うようになり,そのいずれもが意思決定を損なう可能性がある。
有害事象の根本原因解析のチームメンバーは,通常,意思決定の背景にある人的要因を理解する訓練を受けていないため,意思決定が最適でなかったとしても,その可能性を明らかにすることはできない6)。明白で重要な核心の原因より,具体的で測定可能な表面の原因に目を向けがちである。有害事象の根本的原因解析の大き
な障害の一つは,意思決定の背景にある認知プロセスが目に見えないことである。
目に見える薬剤エラーや手技の誤りとは異なり,認知の根底にあるものは,目撃されたかどうかにかかわらず,行動から推測するしかない。認知的な有害事象の根本的原因解析は困難であるが,それなしに安全が損なわれた出来事の背景を理解することはできない。筆者はそれを本書で試みた。この分野には,ほかにも新たな書籍が出ている。そのうちの二つを紹介したい。Jonathan Howard 7)は,症例ベースで神経学における認知エラーと診断エラーについて発表しており,Cym Ryle 8)は, 総合診療医の視点から診断推論の失敗に関する認知的洞察を提示している。これらやそのほかの最近の取り組みとともに,本書は臨床医の総合的な認知キャリブレーションの向上を目的としている。間違いを減らし,より合理的な臨床判断がなされるようになったとき,潮は満ち患者安全への船出となるだろう9)。
本書では,意思決定における失敗や,認知バイアスや感情バイアスによって頻繁に生じる認知エラーを説明するために,実際の症例を紹介する。これらの症例の多くは1990年代から2000年代初頭の約10年間に筆者が救急医療の現場で遭遇したもので,患者のプライバシーに配慮し修正を加えたものである。そして,2005年から現在に至るまで,Dalhousie Medical Schoolの『Applied Cognitive Training in Acute-Care Medicine (ACTAM)マニュアル』として,時折更新しながら,臨床教育に使用してきた。最近では,Sam Campbell(症例11, 12, 30),Terry Fairbanksと同僚たち(症例32),Emil Zamir(症例14)などによって症例が追加された。筆者は彼らの貢献に感謝している。非常に興味深い症例だからだ。残りの章については,全責任の所在は筆者にある。
ACTAMマニュアル発行以来,救急医療のいくつかの側面は変化してきたが,診断の意思決定のための認知的特性はほとんど変わっていない。本書で取り上げる症例の診療環境は偶然に満ちている。救急医療はすべての領域を網羅しているため,本書で取り上げる症例も多彩なものになるのである。さらに,このような状況で本書で取り上げる症例を見てみると,これらは最も未分化なものであり,文脈上の問題やプロセスの本質的な複雑さを示していることが多い10()☞「はじめに」の図I.3参照)。例えば,整形外科や形成外科では,紹介された時点で,ほとんどの症例がすでにかなり整理されているのとは対照的である。症例が学会誌に報告される際にも,同様
に詳細な情報が削除されている。本書で報告された症例は,Gibsonの助言「あなたの頭の中に何があるかではなく,あなたの頭の中がどうなっているかを客観的にみつめてみることだ」11)ということを強調した状況認識のよい例でもある。救急医師の頭の中は「医療エラーの生来の実験室」12)と表現されてきており,さらに認知科学の論文ではバイアスたちの生存競争の場であると広くとらえられている。
本書で述べる認知的分析には,必然的に筆者による認識とバイアスが反映されている。これを医師の思考やエラーを過剰に分析していると思う人もいるかもしれない。しかし,これまでの医学では,臨床推論の思考プロセスの分析に十分な時間が割かれてこなかったので,ここで強調してよいだろう。最後に,本書を2020年という明快な視野を提供してくれる年に出版するというのは皮肉なことである。バイアスがなければ,20/20(両目とも視力2.0)は,われわれに多くを教えてくれるだろう。
文 献
1. Murtagh J. Cautionary Tales: Authentic Case Histories fom Medical Practice. NewYork: McGraw-Hill, 1992.
2. Medical Malpractice Insights. Welcome to Medical Malpractice Insights. Nov, 2014. 《https://madmimi.
com/s/fe6a85#》(2021年6月17日閲覧)
3. Peerally MF, Carr S, Waring J, et al. The problem with root cause analysis. BMJ Qual Saf 2017; 26: 417–22.
4. Croskerry P. Our better angels and black boxes. Emerg Med J 2016; 33: 242–4.
5. Kahneman D. Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus & Giroux, 2011; 85–8.
6. Croskerry P. The need for cognition and the curse of cognition. Diagnosis 2018; 5: 91–4.
7. Howard J. Cognitive Errors and Diagnostic Mistakes: A Case-Based Guide to Critical Thinking in Medicine.
Cham: Springer, 2019.
8. Ryle CA. Risk and Reasoning in Clinical Diagnosis: Process, Pitfalls, and Safeguards. Oxford: Oxford
University Press, 2019.
9. Croskerry P. Becoming less wrong (and more rational) in decision making. Ann Emerg Med 2020; 75:
218–20.
10. Croskerry P. Adaptive expertise in medical decision making. Med Teach 2018; 40: 803–8.
11. Mace WM. James J. Gibson’s strategy for perceiving: Ask not what’s inside your head, but what your
head’s inside of. In: Shaw RE, Bransford J, eds. Perceiving, Acting, and Knowing. Hillsdale: Erlbaum, 1977:
43–65.
12. Croskerry P, Sinclair D. Emergency medicine: A practice prone to error? CJEM 2001; 3: 271–6.
-
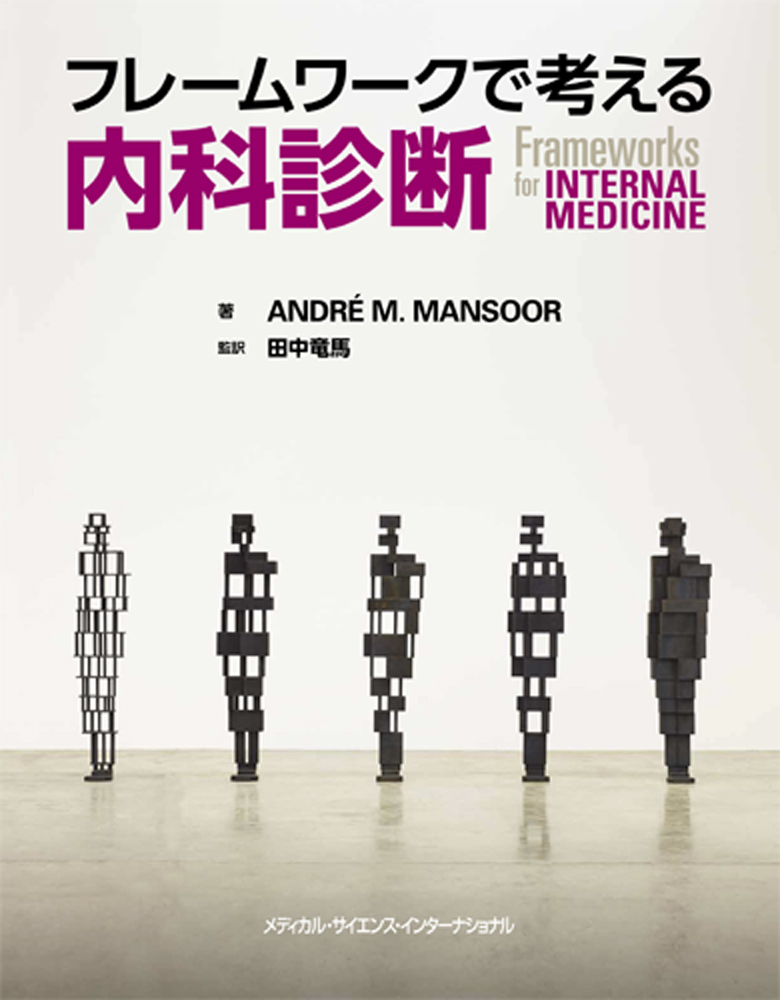
- フレームワークで考える内科診断
- ¥9,130
-

- 総合内科病棟マニュアル 疾患ごとの管理(青本)
- ¥6,160
-

- 総合内科病棟マニュアル 病棟業務の基礎(赤本)
- ¥4,840
-
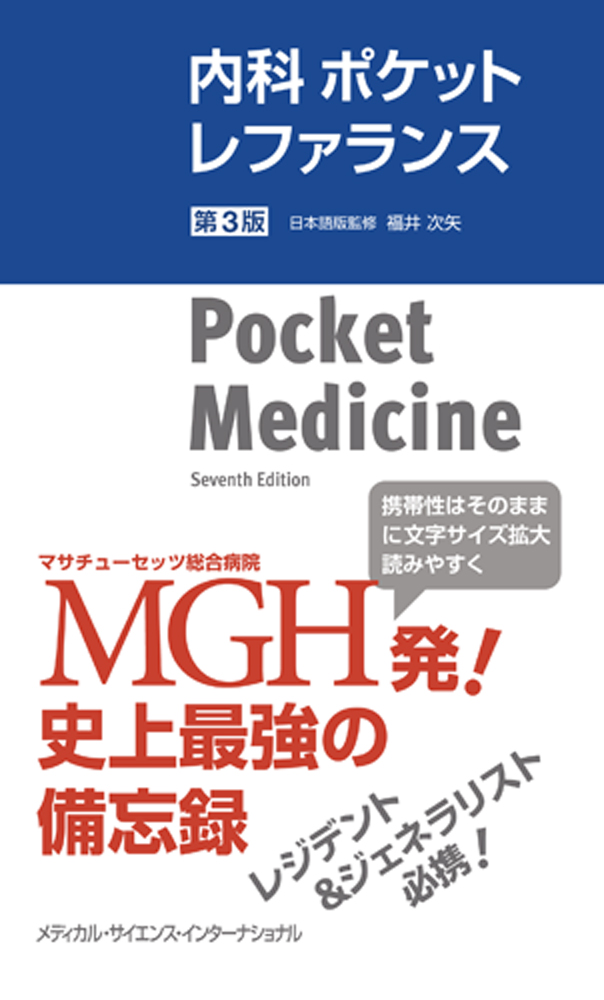
- 内科ポケットレファランス 第3版
- ¥4,620
-
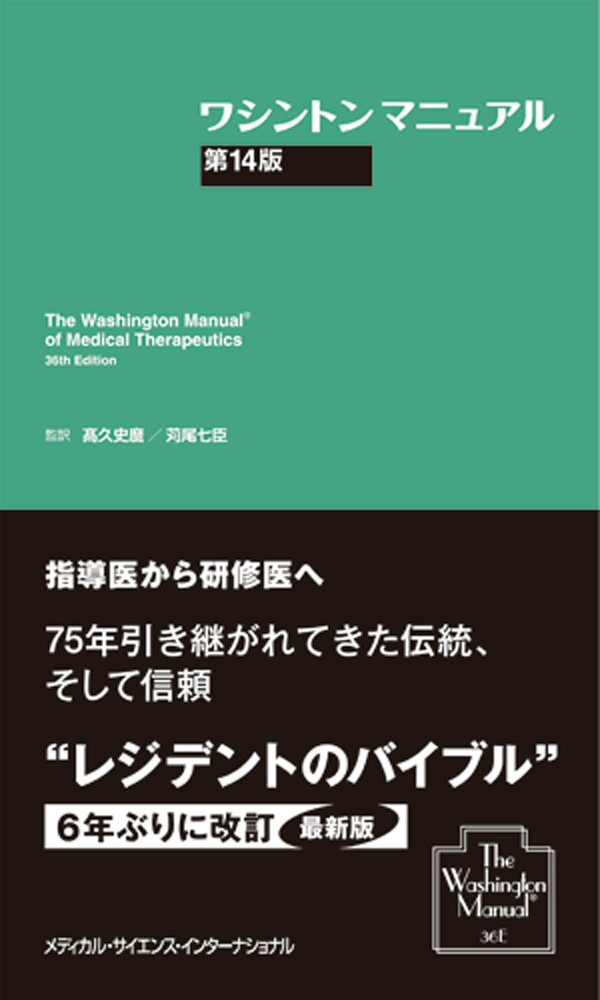
- ワシントンマニュアル 第14版
- ¥9,570
-

- 重症患者管理マニュアル
- ¥7,150
-

- Hospitalist(ホスピタリスト)2020年4号
- ¥5,060
-

- INTENSIVIST(インテンシヴィスト) 2021年1号
- ¥5,060
-

- 関節のMRI 第3版
- ¥14,300
-

- パワーズ運動生理学
- ¥11,000
-

- スポーツリハビリテーションの臨床
- ¥7,700
-

- 不整脈治療薬ファイル 第2版
- ¥5,500
-
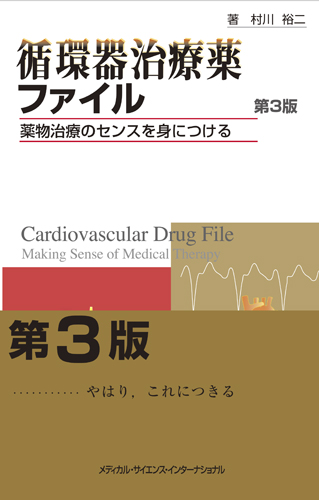
- 循環器治療薬ファイル 第3版
- ¥7,700
-

- 認知症がわかる本
- ¥3,740
-
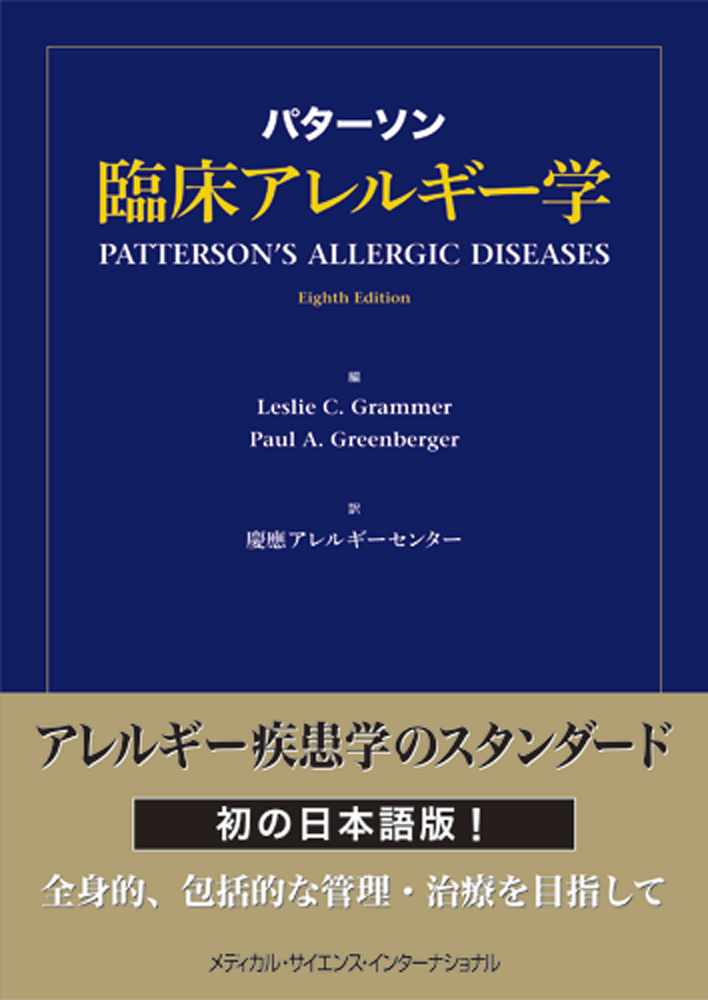
- パターソン臨床アレルギー学
- ¥17,600
-
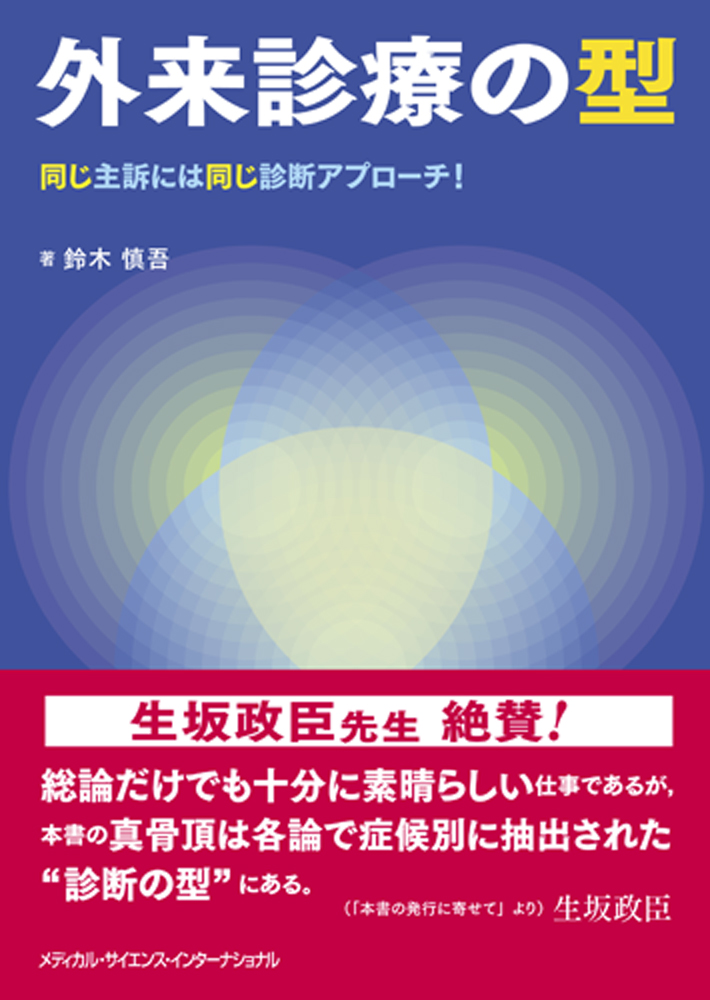
- 外来診療の型
- ¥4,950
-

- ハリソン内科学 第5版
- ¥32,780
-
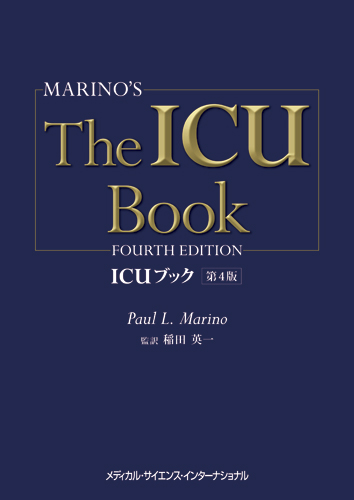
- ICUブック 第4版
- ¥12,100
-
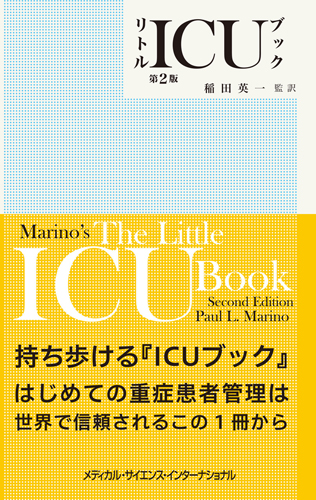
- リトルICUブック 第2版
- ¥5,500
-
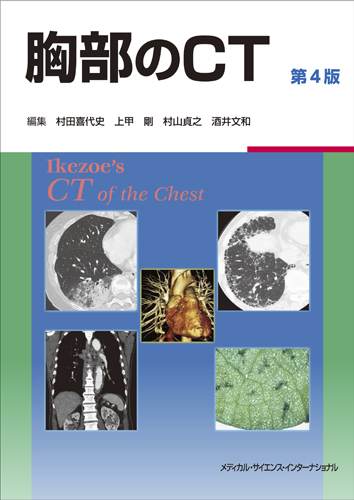
- 胸部のCT 第4版
- ¥16,500
-
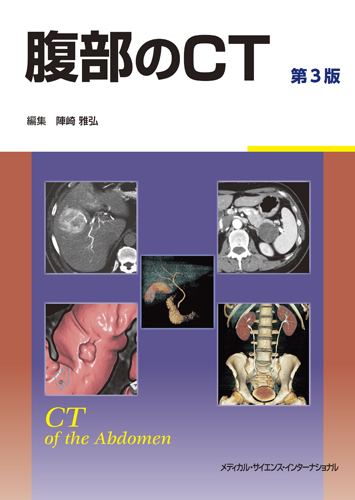
- 腹部のCT 第3版
- ¥14,300
-
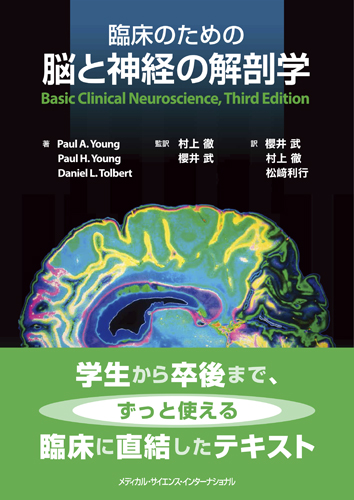
- 臨床のための脳と神経の解剖学
- ¥7,480
-
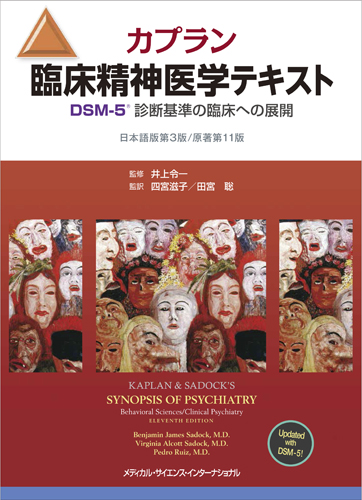
- カプラン臨床精神医学テキスト 第3版
- ¥22,000
-
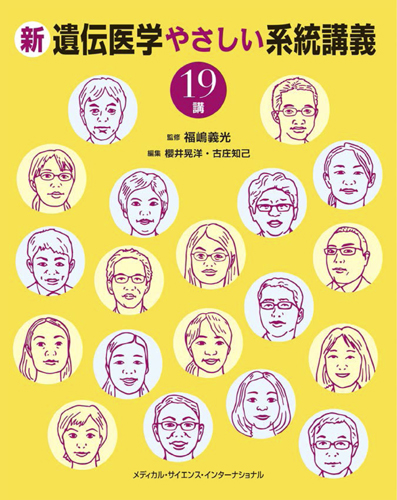
- 新 遺伝医学やさしい系統講義19講
- ¥5,060
-
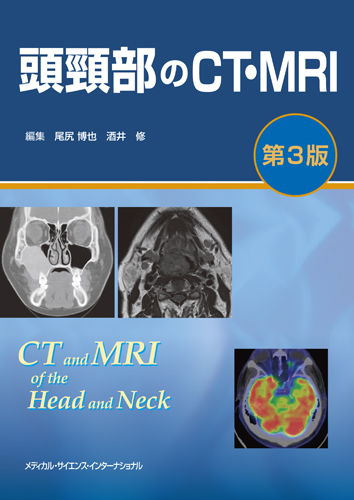
- 頭頸部のCT・MRI 第3版
- ¥16,500
-
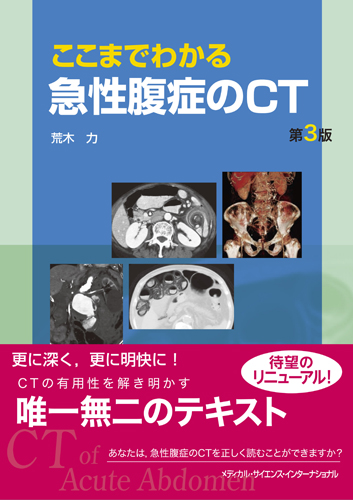
- ここまでわかる急性腹症のCT 第3版
- ¥7,920
-
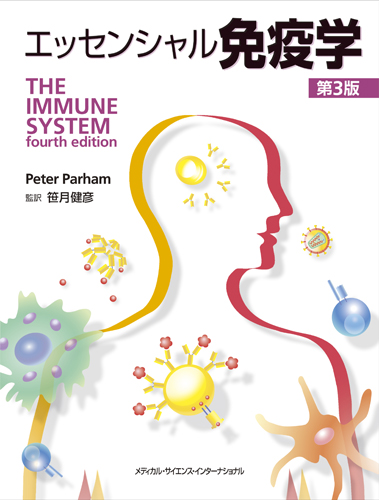
- エッセンシャル免疫学 第3版
- ¥7,040
-
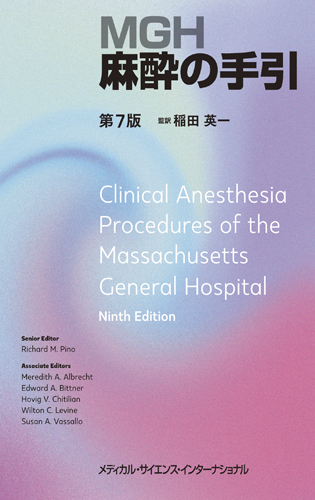
- MGH麻酔の手引 第7版
- ¥8,800








