マインドフル・プラクティス - 医療を支えるマインドフルネス-ある臨床家の実践 -
❝しなやかでタフな,強い自分であり続ける❞——いったんそうした執着は脇に置いて
医療従事者は日々、陰性感情(ストレス・怒りなど)が生じやすい、強い緊張を伴う環境に身を置いている。そうした医療従事者が自身の心を安定させ、患者と人間的に向き合う方法のひとつとして、現役内科医が「マインドフルネス」の考え方・具体的方法を解説した1冊。この領域に興味のある医師をはじめ医療従事者にとって示唆に富む書。
第1章 マインドフルであること
第2章 注意を向けること
第3章 好奇心
第4章 ビギナーズ・マインド
——禅の心で実践する医療
第5章〝いま・ここ〞への意識の集中
第6章 地図のない舵取り
第7章 苦悩に応える
第8章 思いやりの心が揺らぐとき
第9章 悪いことが起きたとき
第10章 癒し手を癒す
第11章 マインドフルになる
第12章 マインドフルな医療を思い描く
謝辞
付録——注意を向ける訓練
原注/訳注/参考文献/索引
ボーナスマテリアル——マインドフルな患者であること
監訳者序文
この本を手にされた方は、医療に携わる方で、おそらく何らかのかたちで〝マインドフルネス〞に興味を持ち、自分自身が携わる医療の質を何か改善できる方法を探したいと考えている方なのではないかと思います。もしそうだとしたら、いま手にされているこの本は、まさにそうした方々のための実用書であるといえます。本のタイトルとなっている〝マインドフル・プラクティス〞は、「マインドフルネスを活かして医療を実践する」ことです。これはマインドフルネスという新しい視点から医療のあり方を問い、個人のレベルで、さらに組織のレベルで医療の質を改善しようとする試みであるといえます。
著者のロナルド・エプステイン先生は、米国東部の都市ロチェスターで家庭医療・緩和ケアに携わる医師であり、ロチェスター大学の家庭医療学・内科学の教授として医学生や多くの医療系学生・研修医などを指導する教育者であり、そして〝医療におけるマインドフルネスの研究〞の先駆者として、この領域における世界で最も有名な研究者の一人でもあります。実際に、本書の日本語版タイトルである『マインドフル・プラクティス』は、エプステイン先生が一九九九年に世界で最も広く読まれている医学誌の一つである米国医師会雑誌(JAMA)において、初めて〝マインドフルネスが医療者に新しい視点を与え、医療の質そのものを変える可能性〞に言及し、その後の多くの研究者や医療者に影響を与えた論文のタイトルでもあります。
マインドフルネスとは〝いま・この瞬間の自分自身、他者、状況に注意を向ける(全集中する)こと〞です。マインドフルネスという言葉は、いまや雑誌や新聞紙面に溢れ、書店に行けば新書コーナーにはずらりとその言葉を冠した書籍が並べられています。そして、その多くはおもに自己啓発本として〝心が落ち着く〞、〝集中力が高まる〞、〝感情をコントールして不安をなくす〞、〝目標を達成する〞、〝人生の扉を開く〞といった目的のための手段として紹介されています。これらは現代社会において、社会人として効率的で、生産的であることが常に要求され、そのような状況で困難に陥ってもなお、しなやかでタフな強い自分であり続けるための手段であるということです。しかし、本来のマインドフルネスが提案する〝いま・ここに注意を向ける〞とは、むしろ逆に〝効率的で、生産的であろうとすることに固執する自分〞、あるいは〝感情をコントロールして、うまく状況を乗り切りたいことにこだわる自分〞の今のあり方に気づくこと、さらに、もしかしたらその状況に苦しむ自分のあり方に気づくことであるといえます。そして、一旦そうした執着を脇に置いて、改めて〝いま・ここ〞にいる自分にとって意味のあるもの、自分をかたち作るものに注意を向けることであるといえます。特に、医療者にとってはこうしたマインドフルネスが提案する注意力、自己のあり方への気づき、柔軟性は不可欠なものです。なぜなら、これらの注意力が自己だけでなく、他者(患者・家族・同僚など)への注意と配慮を生み、そして他者のあり方への気づき、関係の柔軟性を生むためです。医療の本体的な目的は他者への配慮と援助であり、こうしたマインドフルネスは医療者の基本的な姿勢を示しながら、医療の質を支える可能性を持つと考えられます。本書には、まさにそうした〝医療を支えるマインドフルネス〞について、非常に具体的に詳しく書かれています。
本書の特徴は、なんといってもエプステイン先生が、医療者としてあるいは人として自分の半生を 振り返る形で、これまでの患者さんやご家族、あるいは同僚や先輩、後輩の医療者とのエピソードを 紹介しながら、どのようなことに問題意識を持ち、どのようにそれらの問題を検討したかが〝物語〞として記載されていることです。〝物語〞といっても、自分が経験したことを武勇伝や誇張を織り交ぜながら〝お話〞として語っているのではなく、研究者として自分の体験を分析し、それが学術的にどのように説明できるのかを極めて冷静な視点で、ときに医療者としては正直すぎるとも言えるほど率直に、ご自身が心の中で思ったことも含めて記述されています。そして、個々のそうした出来事がマインドフルネスの視点からはどのような体験として捉えられるのか、それがどのように医療の質を改善するのかについて一つひとつ丁寧に考察されています。
翻訳にあたって、〝マインドフル・プラクティス〞に特に関連する文章は、ゴシック書体にして強調しています。もしこの本をたまたま手に取ってご覧になっている方は、パラパラと太字の部分とその周辺の文章だけを追って読んでいただくのでもよいと思います。おそらくそこには、皆様が日常の臨床現場で遭遇する悩み、困惑、違和感に該当する記述があると思います。そしてそれらに対する答えのヒントがその前後に記述され、何らかの思索のきっかけとなるのではないかと思います。
さらに、既にマインドフルネスに精通している方にとっては、巻末に収録されている原注も非常に役に立つと思われます。研究者であり、教育者でもあるエプステイン先生が、一つひとつの体験に関連する論文を詳しく調べ、丁寧に解説をされています。さらに、より内容理解の助けとなるように、翻訳にあたり訳注として解説や文献を追記しています。それらの解説や論文すべてを読むには膨大な時間がかかりますが、該当箇所に紹介されている記述を参考にご自身が興味を持った論文から検索して読み進めていただければと思います。
少しだけ私とエプステイン先生との出会い、そしてご一緒した経験を共有させていただきます。私がエプステイン先生に初めてお会いしたのは、二〇一四年に東京で開かれた招聘講演会の会場においてでした。この講演会で、エプステイン先生はまさに〝マインドフル・プラクティス〞のお話をされていましたが、当時の私はマインドフルネスについてはその言葉を聞いたことがあるのみで、その言葉が意味することがわからず(むしろ〝怪しい〞かも?と感じつつ)、講義の価値も十分に理解していませんでした。しかし、その講演会をきっかけにロチェスター大学で開かれている四泊五日の医療者向けのワークショップに二〇一五年と二〇一六年に参加させていただくこととなり、日常の診療で日々悩む問題をテーマにしながら、参加者の興味を引く工夫を凝らされたワークを通して、〝マインドフルネス〞が医療者を、そして医療をどう支え得るのかを体験的に学ぶ機会をいただきました。
そして、何よりも二回目に参加した二〇一六年のワークショップの直前に恒藤暁先生(京都大学医学部附属病院緩和医療科)らとともに、日本への招待の御礼としてエプステイン先生のご自宅でのホームパーティにお招きいただいたときのことが忘れられません。ご自宅では、エプステイン先生はもちろん、本書にも登場する奥様デボラ(デッブ)さんや、ワークショップの講師であるミック・クラスナー先生や、トニー・バック先生ともマインドフル・プラクティス・ワークショップの設立の経緯やそこに懸ける思い、また普段の診療での思いや迷いなどのお話をさせていただきました。そして、エプステイン先生の手料理(美味しい!)やワインを味わい、さらには(プロのミュージシャン並みの!)先生方が奏でる音楽を聴きながら、まさに五感で先生方のその人柄や、医療や教育の仕事に対 する本当に真伨な姿勢を間近に感じさせていただきました。
エプステイン先生はちょうどこのワークショップの滞在中に本書の構想について話をされており、二〇一七年に発刊された後に、早速読ませていただき感銘を受け、身近な同僚にも紹介をしておりました。しかし、この実用書を日本語で読むことができたらより身近に〝マインドフル・プラクティス〞の情報を共有し、さらに日本の医療の文脈に合わせて深い議論ができると常々考えておりました。その折に、ある日出版社を通じて塚原知樹先生が本書の翻訳本の原案を作成されたとうかがい、感動しました。そして、検討と準備を重ね、ついに発刊の運びとなりました。発刊に向けて、さまざまな交渉を重ねご尽力くださった編集者の水野資子様、柴田優子様にこの場を借りて改めて御礼申し上げます。
改めて、本書はマインドフルネスの啓発本ではなく、臨床現場の医療の質を改善する目的で書かれています。翻訳にあたっては〝マインドフル・プラクティス〞のエッセンスを具体的に伝えようとするエプステイン先生の率直で思慮深い語りの口調を崩さないように注意し、出来るだけ平易な表現になるように努めました。本書が日本の医療現場へ広く行き渡り、医療者と医療を支えるための一つのきっかけとなることを強く願っています。
土屋静馬
訳者序文
翁は病人を見ている間は、全幅の精神を以って病人を見ている。そしてその病人が軽かろうが重かろうが、鼻風だろうが必死の病だろうが、同じ態度でこれに対している。
――森鷗外『カズイスチカ』(一九一一年)より
もし誰かに「瞑想したほうがいい」と言われたら、あなたはどう答えるだろうか?「いいですね!」かもしれないし、「瞑想ですか?」かもしれない。では、「全幅の精神をもって病人を診る方法を学ぼう」と言われたら、どうだろうか?鷗外の意図はさておき、この近代的な日本語ほど本書のテーマを言い表すのにぴったりな言葉はないのではないかと訳者は考えている。
「全幅(full )の精神(mind )を以って」診療することは、いつの時代と場所でも大切であり続けた。冒頭の「翁」は鷗外の父がモデルであるが、一〇〇年以上経った米国の本書にも、「余命数日の患者を診察した直後であっても、その次に来た足先をぶつけたという患者を同じ集中力で診察する」とある。そしてそれは、〝いま・ここ〞を生きるあなたにとっても大切であるはずだ。
読後に診療の質と充実度が向上したことを実感し、出版先も決まらないうちに翻訳を始めた訳者としては、本書があなたの何かを豊かにすることを確信している。なお、鷗外は翁が「盆栽を翫もてあそんでいる時も」病人を診るときと同様の心構えだと言い、本書の著者は、カヤックやチェンバロでの気づきを診療に活かしている。本書に出会ってから、ピアノを弾いて力の抜き方や心構えなどを訓練するようになった訳者としては、読んだ後であなたの生活に何か変化が起きても、責任を負えないことをお断りしておく。
最後に、監訳をご快諾くださり、訳文の質と正確さ、出版することの意義を段違いに引き上げてくださった土屋静馬先生、持ち込まれた企画を粘り強く成立させてくださったメディカル・サイエンス・インターナショナル社の水野資子さま、緻密な作業により美しく静かな文章とレイアウトに仕上げてくださった同社の柴田優子さまに、深く感謝する。
塚原知樹
-
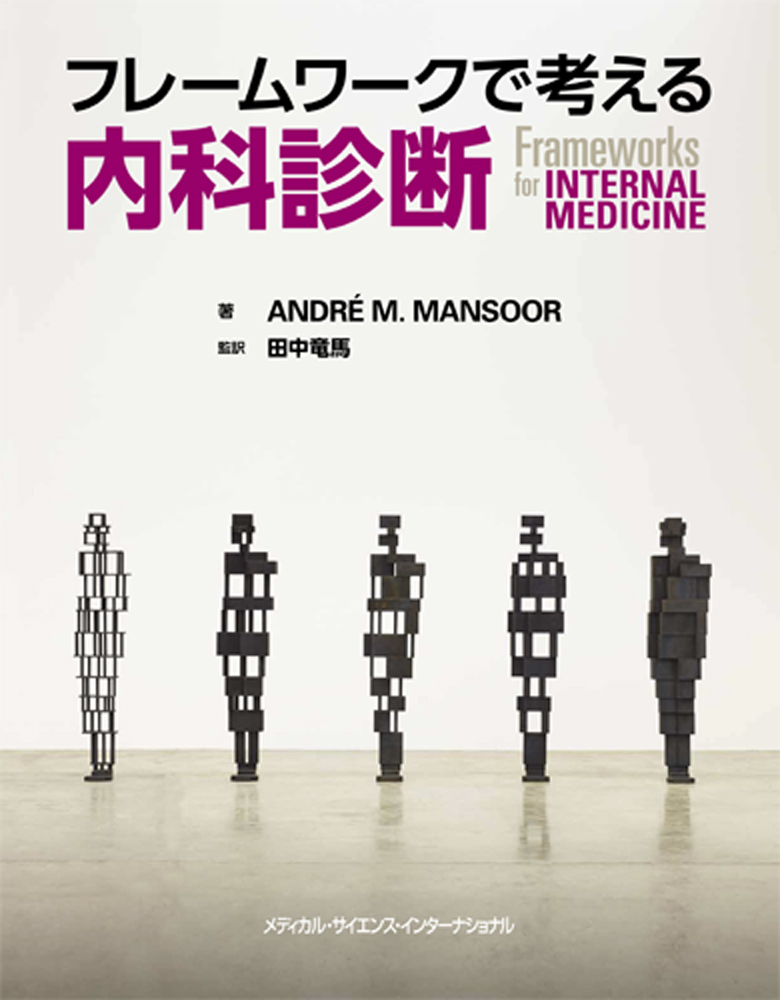
- フレームワークで考える内科診断
- ¥9,130
-

- 総合内科病棟マニュアル 疾患ごとの管理(青本)
- ¥6,160
-

- 総合内科病棟マニュアル 病棟業務の基礎(赤本)
- ¥4,840
-
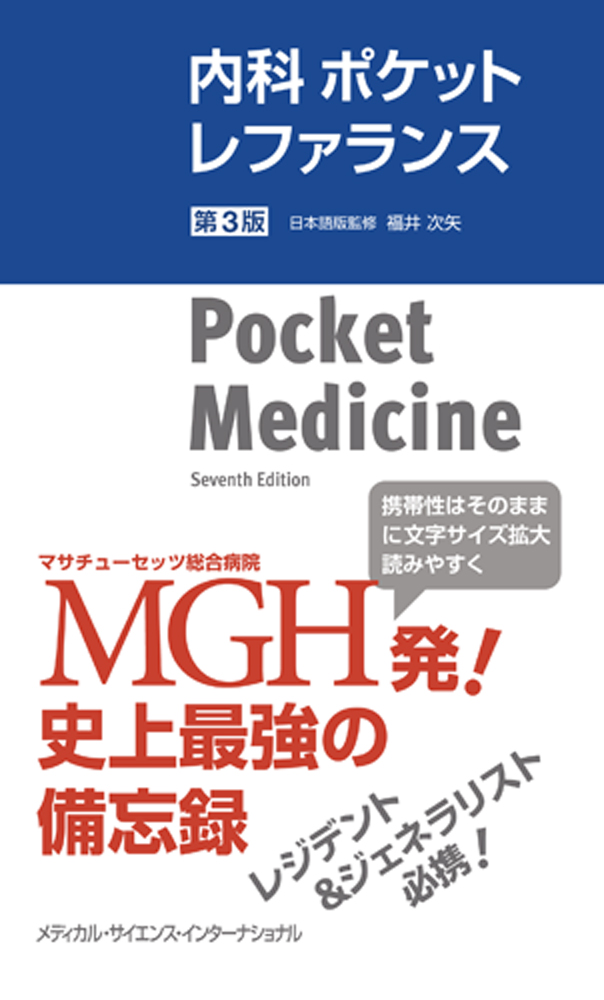
- 内科ポケットレファランス 第3版
- ¥4,620
-
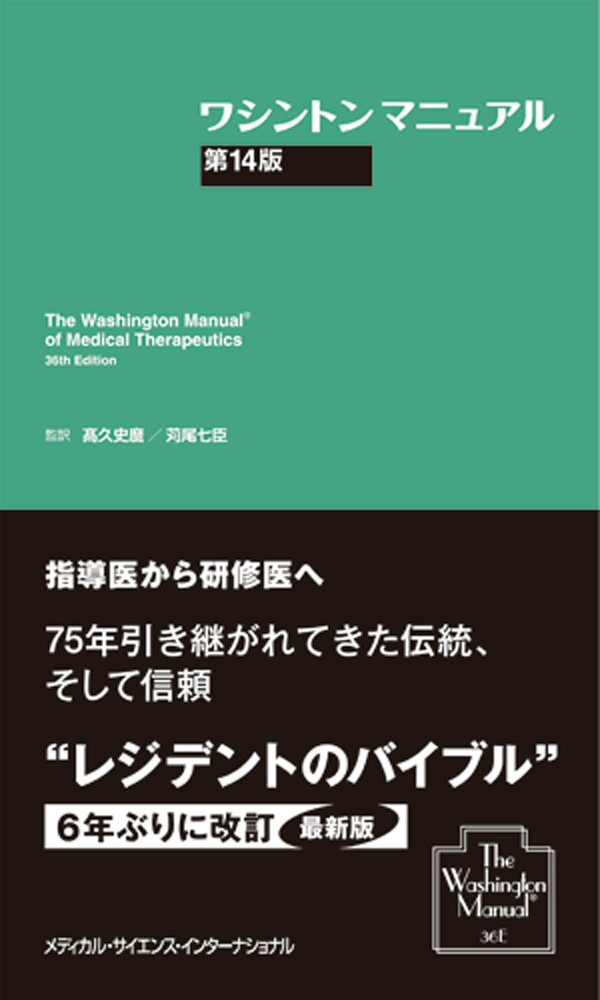
- ワシントンマニュアル 第14版
- ¥9,570
-

- 重症患者管理マニュアル
- ¥7,150
-

- Hospitalist(ホスピタリスト)2020年4号
- ¥5,060
-

- INTENSIVIST(インテンシヴィスト) 2021年1号
- ¥5,060
-

- 関節のMRI 第3版
- ¥14,300
-

- パワーズ運動生理学
- ¥11,000
-

- スポーツリハビリテーションの臨床
- ¥7,700
-

- 不整脈治療薬ファイル 第2版
- ¥5,500
-
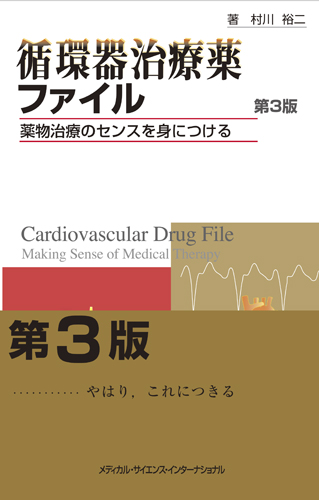
- 循環器治療薬ファイル 第3版
- ¥7,700
-

- 認知症がわかる本
- ¥3,740
-
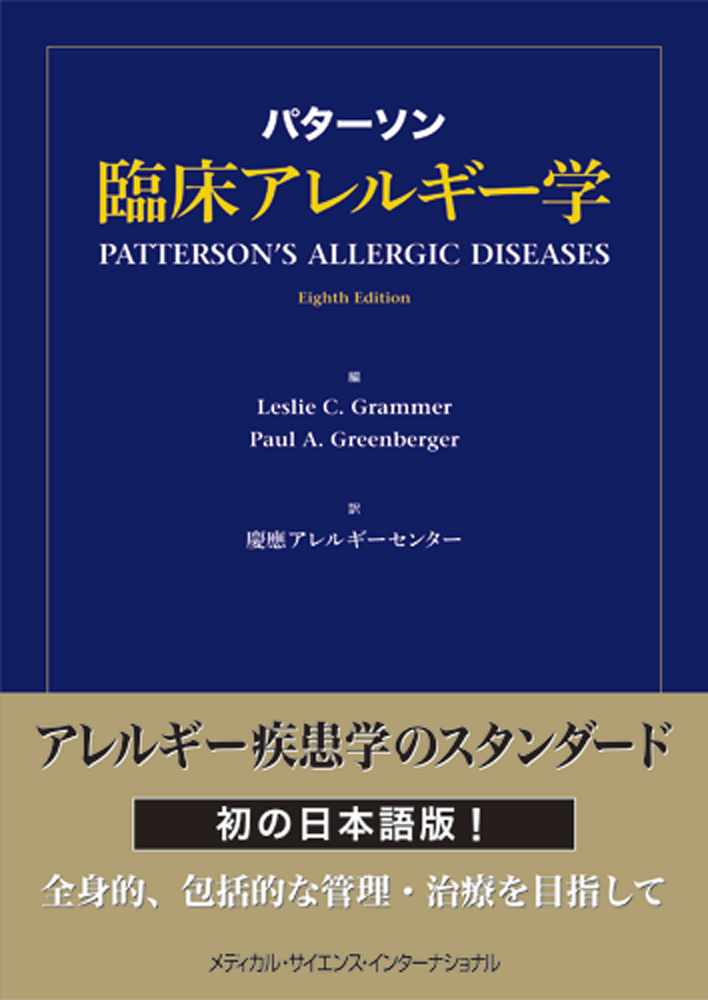
- パターソン臨床アレルギー学
- ¥17,600
-
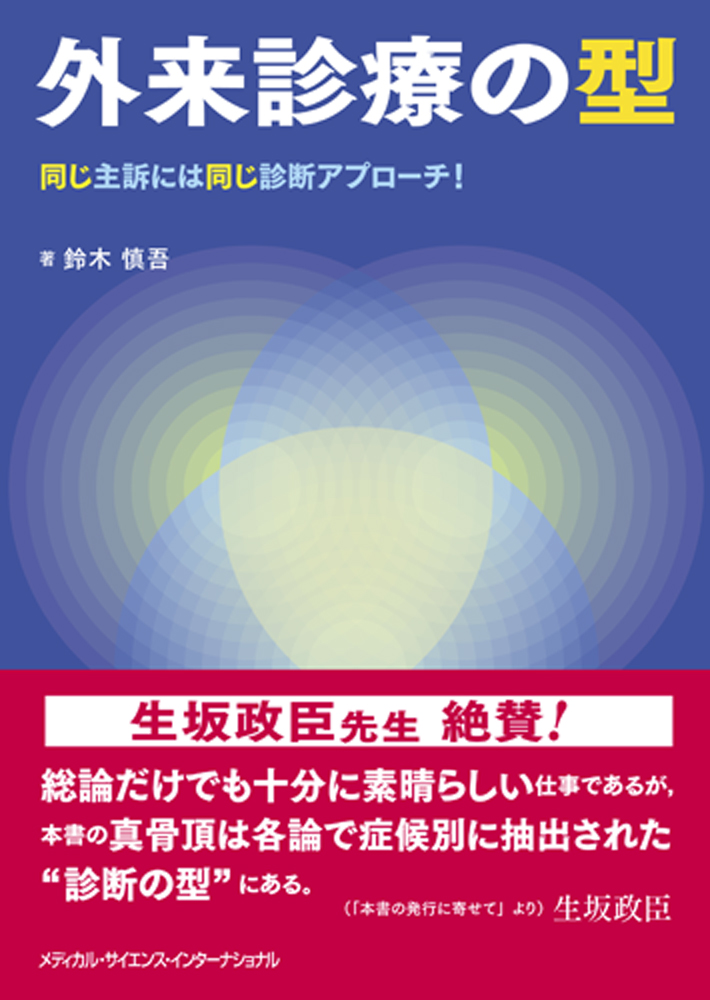
- 外来診療の型
- ¥4,950
-

- ハリソン内科学 第5版
- ¥32,780
-
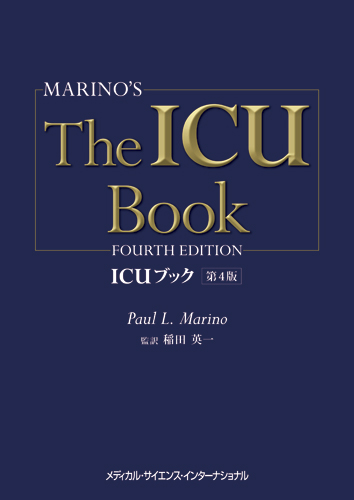
- ICUブック 第4版
- ¥12,100
-
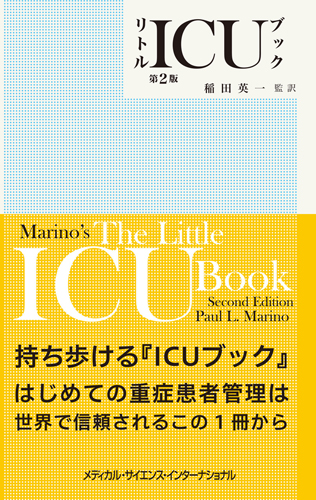
- リトルICUブック 第2版
- ¥5,500
-
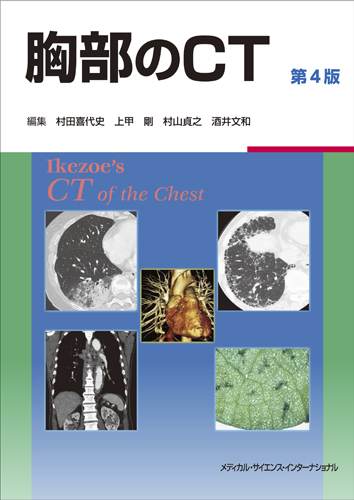
- 胸部のCT 第4版
- ¥16,500
-
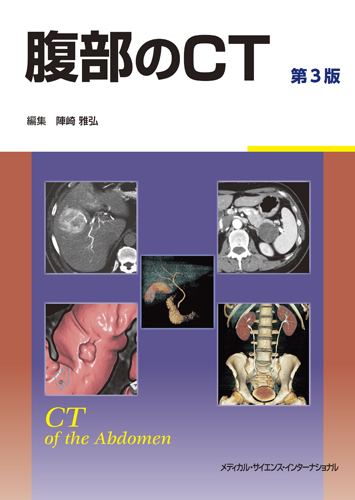
- 腹部のCT 第3版
- ¥14,300
-
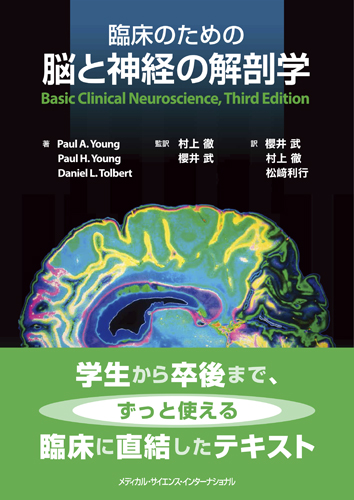
- 臨床のための脳と神経の解剖学
- ¥7,480
-
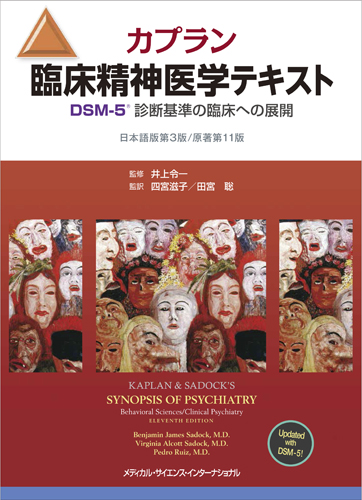
- カプラン臨床精神医学テキスト 第3版
- ¥22,000
-
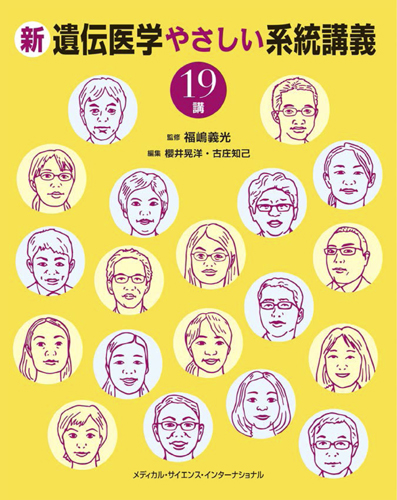
- 新 遺伝医学やさしい系統講義19講
- ¥5,060
-
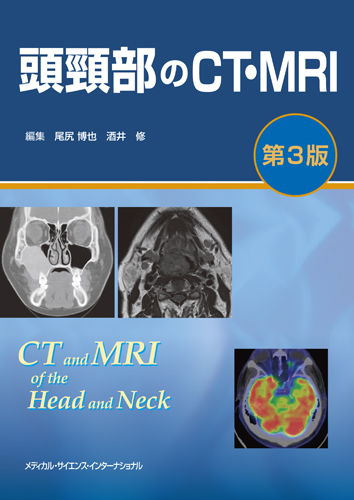
- 頭頸部のCT・MRI 第3版
- ¥16,500
-
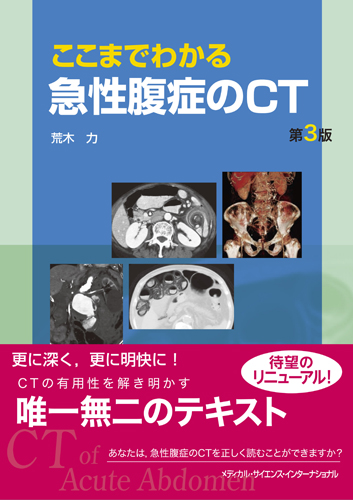
- ここまでわかる急性腹症のCT 第3版
- ¥7,920
-
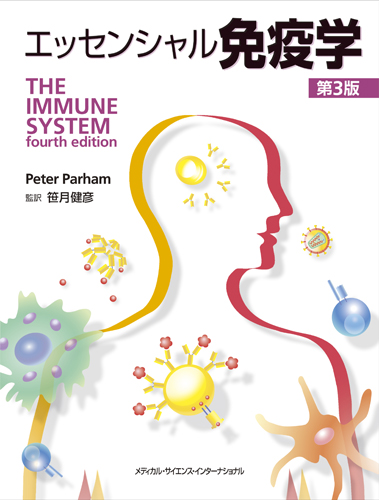
- エッセンシャル免疫学 第3版
- ¥7,040
-
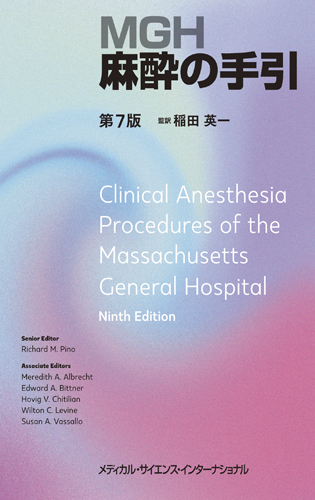
- MGH麻酔の手引 第7版
- ¥8,800









